今度最終面接がある。
絶対合格したい。どうやって対策するのがいいの?
この記事を読むとわかること
それでは早速解説していきます。

最終面接まで来ることができたなら、内定はもうすぐそこですね。
ただ内定をもらうためには、最終面接の特徴をしっかり理解しておくことが重要です。
以下が具体的な最終面接の特徴です。
順番に説明します。
最終面接では役員や社長が面接官となります。
え、面接官を理解することはなんで重要なの?
答えは、面接官によって面接のスタイルを変えるべきだからです。
1次面接を担当する人事は、役員や現場社員が行う二次面接や最終面接に「やばい学生」を上げて怒られたくないため、どちらかというとベーシックな質問をします。
なので、一次面接はネガティブチェック(減点方式)の面接と言われています。
>> 一次面接の対策方法を知りたい人はこちら
しかし、最終面接で出てくる百戦錬磨の役員や社長は見ている点が違います。
「この人と一緒に働きたいか、この会社を任せても大丈夫か」という観点で面接をします。
なので一次面接を同じように面接を受けても内定をもらえる可能性が低いですし、最終面接では入社意欲がめちゃめちゃ大事なんです。
みなさんにとっては「内定」が就職活動のゴールかも知れません。
ですが、企業にとっては「内定承諾」が採用活動のゴールです。
そのため、内定を出したら絶対にうちに来てくれると思う学生に内定を出します。
内定を蹴りそうな学生には内定は出さないという企業がほとんどです。
では絶対にうちに来てくれると判断する時の判断軸は何でしょうか?
当たり前ですが答えは、入社意欲です。
入社意欲を見て「内定を出すに値するか」決めているんですね。
余談ですが、最終面接まで行けている時点でみなさんの能力は認められています。
最後に差をつけるのは「入社意欲」です。
最終面接は対策が非常に難しい面接となっています。
理由としては
といった感じです。
じゃあ最終面接は対策できないってこと?
そんなことはありません。
今から最終面接の対策方法を紹介します。

最終面接の対策として、最終面接前にするべきことは以下の2つです。
めちゃめちゃ大事なので、しっかり解説します。
最終面接で出てくる役員や社長は常に事業の将来について考えています。
それはもちろん、競合他社にどのようにして競合優位性を築いていくのかというのも含まれます。
そんな人たちの前だからこそ、小手先の企業分析では太刀打ちできません。
仮に一次面接と二次面接、小手先の企業分析で挑んで通過できたとしても、それでは最終面接で落ちる可能性が全然あります。
なので、企業分析を徹底的に行いましょう。
みなさんは感情を面接で伝えるのが得意ですか?
私は正直、めちゃめちゃ苦手でした。
でも先程から伝えているように、最終面接で一番大事なのは、入社意欲です。
絶対に入社をしたいという感情が「内定」出しの有無を決めます。
なので、面接で感情を出す練習をしましょう。
最終面接と同じ緊張感で模擬面接をやることをおすすめします。
面接官を本物の役員や社長だと捉え、必死に熱意を伝える練習をすることで、本番でも同じことができるようになります。
>> 私が30回以上やって編み出した模擬面接のやり方を知りたい人はこちら
最終面接の通過率は50%と言われています。
なので、2人に1人は受かる計算です。
だからこそ、絶対受かりたいですよね。
そう思う人は上記の対策を徹底して行うようにしましょう。
最終面接の対策方法は…

ここからは最終面接を通過するコツを紹介します。
具体的には以下の4つを意識すると良いです。
先ほどから何回か言っていますが、入社意欲が最終面接において最も重視されているポイントです。
それは企業と学生のゴールにギャップがあるからでしたよね。
逆に言うと、入社意欲を前面に押し出すことができ、企業に「私は内定を絶対に蹴りません」と伝えることができれば、最終面接を通過する可能性は大幅に上がります。
例えば、私は〇〇部で絶対に挑戦したいことがあります。それは△△です。それを成し遂げることができたら、社会に大きなインパクトを与えられると思っています。そんな未来にワクワクしています。なので御社で働きたいんです!
と面接で言ったとしましょう。
どうですかね?入社意欲が伝わりませんでしたか?
ここでのポイントは、ただ単に御社に入社したいんですと言うのではなく、御社でやりたいこと(御社でしかできないこと)を言うことです。
これをすることで、入社意欲がめちゃめちゃ伝わります。
先程、役員たちは事業の将来について常に考えているということを話しました。
なので、そこに積極的に自分の意見を持ち込みましょう。
偉い人たちが考えていることに口を突っ込んでいいの?
全然大丈夫です。
むしろ事業について話せるレベルにあると言うことで、歓迎されることが多いです。
ただ、もちろん自分の意見をしっかりもっておくことが前提です。
実は役員や社長は問題意識を持って、事業を一緒に改善していける人材をいつも求めています。
それは新卒でも中途でも変わりません。
なので、自分が事業に対して問題意識を持って改善していけるんだというのを伝えましょう。
これをすることで、「この人となら一緒に働きたい」と思わせることができるでしょう。
結局は役員が「一緒に働きたい」と思えば、採用になるのが最終面接です。
究極のことを言うと、人事や現場が「NO」と言っても役員が「YES」を出せば、内定が出ます。
ではどうやって役員に「一緒に働きたい」と思わせることができるでしょうか?
この一つの方法に「気持ちよく話させる」という方法があります。
「〇〇さんは御社でたくさんの経験をされてきたと思います。そのなかで、1番思い出に残っていることってなんでしょうか?」
これを逆質問の時に聞くことで、役員は気持ちよく武勇伝を語ってくれるでしょう。
>>最終面接で聞くべきおすすめの逆質問を知りたい人はこちら
気持ち良くなった状態で面接を終えることができれば、面接官である役員は、
 役員
役員
この子は気持ちよく面接できたな、採用するか。
となるのです。
そんなの適当だろ…という人もいるかも知れませんが、実際におじさんが理不尽に決定している光景を何回も人生で見たことあると思います。
それが現実なのです。
最終面接という特殊な場ではあるものの、一次面接や二次面接と同様に「なぜ自分を採用するべきか」というのをしっかりと伝えましょう。
この時に1次、2次面接と伝えることに矛盾がないように気をつけましょう。
最終面接を通過するコツは…

ここからは最終面接で気をつけることを解説します。
具体的には以下のことに気をつけましょう。
1次面接、2次面接との一貫性は非常に重要な点です。
その割に、ここにしっかりと注意を払っている就活生は少ない印象を受けます。
最終面接では「絶対に内定もらいたい」と思う気持ちが強いあまり、今までの発言と矛盾してしまうことを言ってしまいがちです。
特に自分をよく見せようと、今までの発言と違う発言をする場合が多いように感じます。
1次、2次面接との一貫性には注意をしっかり払いましょう。等身大の自分を出すのがコツです。
最終面接で一番大事なのは、入社意欲でしたね。
そうにもかかわらず、入社意欲を前面に押し出していない人を多く見かけます。
例えば、「弊社は第一志望ですか?」と聞かれた時に
「第一志望群」です。
と答えている人がいます。
これは「御社は第一志望ではありません」と伝えているようなものです。
最終面接では絶対に「御社が第一志望です!」と伝えるようにしましょう。
役員クラスの面接官は「深く難しい質問」をかけてきます。
といったような質問です。
すぐに答えるのは難しいですよね。
このような質問には、ゆっくりと時間をかけて回答するようにしましょう。
1番最悪なパターンが思いつきで答えてしまい、役員に深掘りされてボロが出てしまうパターンです。
思いつきで落ちるくらいであれば、ゆっくり考えて自分にとって1番正しい解答をできるようにしましょう。
最終面接で気をつけるポイントは…
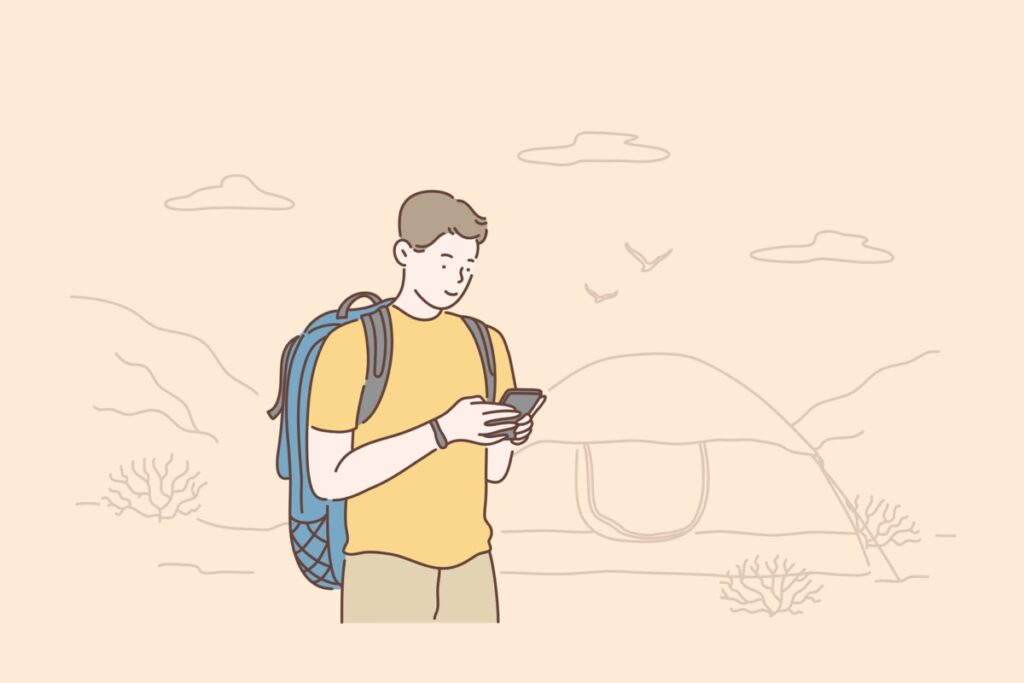
ここからは最終面接で落ちた時に見直すべきポイントを紹介します。
チェックポイントは以下の2つです。
志望動機とか入社意欲をしっかりアピールしているのに落ちてしまうのはなぜ?
こんな疑問を持っている人がいると思います。
結論、熱意が足りていないからです。
私も気持ちを伝えるのが苦手なタイプなのでよくわかりますが、熱意を伝えないといくら志望動機や入社意欲を伝えたところで落ちてしまいます。
当たり前ですが、本当に人生を賭けてやりたいことの話をしている時には、思いがこもって、熱く話してしまいます。
面接官としっかりキャッチボールできていないことも面接を落ちてしまう原因になります。
最終面接だと張り切って自分の言いたいことだけをずっと言ってしまうのでは、会話のキャッチボールができません。
相手から来た質問に対して適切な分量で答え、相手にボールを返してあげることで会話は成り立ちます。
なので、もし最終面接で落ちてしまう場合は、会話のキャッチボールがしっかりできているのか確認しましょう。
ここまで読んでいただいて、大変嬉しいです。
今回は最終面接の対策方法を総合的に解説しました。
最終面接まで来ている皆さんはあと少しで内定です。
皆さんの内定を祈っています。
人気の記事
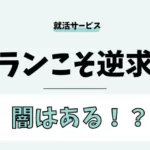 1
1
Fラン生こと逆求人使って欲しいんですが、話題の逆求人サイトってスカウトが来るって聞いたんだけど、なんか怪しいんだよな。 みたいな事を思ってる人も多いのでこういった疑問を解決します。 この記事を読むとわ ...
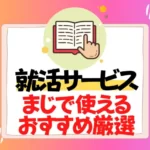 2
2
私は23卒就活生でしたが、早期選考で某有名ITベンチャーから内定をもらい、就職活動を終えました。 就職活動自体は半年ほど行なったのですが、その中で自分が愛用していたサイトやサービスを今回はまとめていき ...