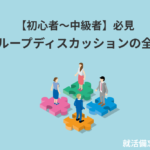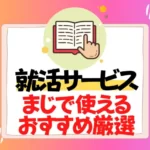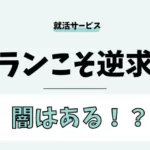グループディスカッション
グループディスカッションの流れを徹底解説【おすすめの進め方も紹介】
wp-content/uploads/2022/01/kaisya_komaru_man.jpg"/>
グループディスカッションがどんな流れで進んでいくのか知りたいです。
おすすめの進め方とかありますか?
こういった疑問を解決します。
この記事を読むとわかること
- グループディスカッションの流れ
- グループディスカッションの中で注意するべきこととコツ
- グループディスカッションの事前準備
wp-content/uploads/2022/10/cropped
この記事を読めば「グループディスカッションの流れと進め方」などが分かります。
全て詰め込んだ結果、5000字を超える記事となっていますが、最後まで読んでもらえると嬉しいです。
それでは早速解説していきます!
グループディスカッションとは
wp-content/uploads/2022/03/s-36-1024x683.jpeg" alt="" class="wp-image-5312"/>
グループディスカッションとは、グループになって、与えられたお題への結論を時間内に出すというのが一般的な解釈です。
お題としては、
「スターバックスが売上を2倍にするにはどうすればいいのか?」
などのビジネス的なものから、
などの抽象的なものまであります。
通常は5人程度のグループでディスカッションをして、結論まで導いていく形になります。
議論のアウトプットを見ているわけではない
就活生でよくあるのが、「グループディスカッションは議論のアウトプットが一番大事だ」という勘違いです。
私はグループディスカッションでは、「周りの就活生とどのように協力し、アウトプットまで持っていくのか」が重要だと思っています。
wp-content/uploads/2022/10/cropped
なぜなら、アウトプットが一番大事なら「グループでやる必要がない」からです。
グループディスカッションの評価についてもっと知りたい人は以下の記事を参考にすると良いでしょう。
グループディスカッションの流れを徹底解説
wp-content/uploads/2022/03/s-33-1024x683.jpeg" alt="" class="wp-image-5309"/>
まずはグループディスカッションの流れを徹底的に解説します。
8つのステップに分けて解説するので、ぜひ最後まで見てください。
- 試験官からお題が出される
- 自己紹介(お題が出される前にある場合もある)
- 役割決め
- 時間配分決定
- 前提の確認
- 議論を進める(進め方はたくさんあるので割愛)
- 結論を出す
- 発表する(パワポで発表などもある)
グルディス初心者の人へ
グルディス初心者で何も分からないという人は、以下の記事をまずは確認すると、グルディスへの理解が深まるかもしれません。
ステップ①:試験官からお題が出される
グループディスカッションの始まりはシンプルで、試験官から以下の項目が共有されてディスカッションが始まります。
試験官から共有される内容を細分化すると以下のようになります。
イメージとしては、
「それではグループディスカッションを始めたいと思います。お題は〇〇で、時間は30分、発表はパワーポイントなどを使ったプレゼンテーション方式で、発表時間は3分でお願いします。それでは今からグループディスカッション開始です」
といった流れで始まります。
ステップ②:自己紹介
グループディスカッションが始まったら、まずは軽く自己紹介をしましょう。
自己紹介は名前・グループディスカッションの経験の有無くらいで良いでしょう。
たまにグループディスカッションが始まる前に自己紹介をさせてもらえる時もあります。
そういった時はグループディスカッションが始まった後に改めて、自己紹介をする必要はありません。
ステップ②の自己紹介がステップ①よりも前に来るイメージです。
wp-content/uploads/2022/10/cropped
自己紹介で時間を使うのは勿体無いので、当たり障りのない内容を軽くしゃべればOKです。
ステップ③:役割決め
自己紹介が終わったら、グループディスカッションにおける役割決めを行いましょう。
グループディスカッションにおける役割は以下のものがあります。
- リーダー(ファシリテーター)
- 書記
- タイムキーパー
- その他
性格や能力でやるべき役割は違う
みなさんの性格や能力によって得意・不得意な役割があります。
なので、もしわからない場合は、以下の記事を参考にすることをおすすめします。
最初、何をすればいいのかわからないうちは何も役割がない「その他」になるのがおすすめです。
ステップ④:時間配分の決定
それぞれが行う役割を決定したら、次は時間配分の決定です。
時間配分を決定することで、以下のようなメリットがあります。
- 議論が長くなったときに次に推し進められる
- 議論全体のイメージがつく
特にグループディスカッションで多いのが、議論が白熱してしまい、時間がなくなってしまうことです。
それを避けるためにも大体の時間を設定し、時間を過ぎている場合は無理矢理にでも次の検討ステップに移行できるように時間配分を決定しましょう。
グループディスカションで一番大事なのは最後に出るアウトプット
グループディスカッションで一番大事なのは、最終的に出るアウトプットです。
なので、しっかりと結論まで辿り着き、アウトプットを発表できるような時間配分を行うようにしましょう。
グループディスカッション初心者の人は他の人に時間配分の決定は任せましょう。
ステップ⑤:前提の確認
時間配分の決定が終わったら、次は前提の確認に入ります。
前提の確認とは、お題に関して共通認識を持っておくべきことに対して、みんなで認識を揃えることです。
例えば、「とあるラーメン屋の売り上げを2倍にしてください」というお題だったとしましょう。
その場合は、まず「このとあるラーメン屋とはどこなのか」や「2倍にするためにかけていい期間がどれくらいなのか」などの前提認識をみんなで揃える必要があります。
wp-content/uploads/2022/10/cropped
チェーンのラーメン屋や個人店の違いで取れる戦略の幅が大きく変わりますからね。
前提確認はかなり重要
前提確認は個人的にはかなり重要なパートだと思っています。
なぜなら、前提認識がずれていたり、しっかり行われていないとその後の議論に影響するからです。
初心者の方も前提認識の共有には積極的に参加しましょう。
自分の中でわからないことや微妙だなと思うことは、ここで認識を揃えておくことで後で議論の最中の違和感を消すことができます。
ステップ⑥:議論を進める
前提の確認が終わったら、議論を進めていきます。
議論の進め方はテーマによって変わってきます。
ちなみにグループディスカッションのテーマは以下の3つに大きく分けられます。
なので、上記3つのテーマそれぞれに議論の進め方があるといった感じにあっています。
テーマごとの議論の進め方を知りたい人は以下の記事にて確認することをおすすめします。
後戻りがないように議論するのが重要
議論を進めるときのポイントは、後で戻ってくることがないように一つ一つしっかりと潰していくことです。
後で「そういえばここってなんでこの施策を取ることになったんだっけ?」のように、議論し終わった箇所をもう一度議論するのは時間の無駄になってしまいます。
なので、しっかりと一つ一つ合意をとりながら議論を進めていきましょう。
ステップ⑦:結論を出す
議論を進めることができたら、結論を出しましょう。
グループディスカッションごとにお題があるので、そのお題に沿って結論を出しましょう。
イメージとしては以下のような感じです。
- とあるラーメン屋の売り上げを2倍にせよ→結論:店で一番売れているラーメンとサイドメニューを組み合わせたセットメニューを作り、客単価を上げる
- 幸せな人とは?→結論:ストレスがない人
- 大学生が将来のために絶対にやるべきこと→結論:友達づくり
結論がお題に対して適した回答になっているか
結論を出すときのポイントは、お題に対してちゃんと回答になっている結論を作ることです。
ここでお題に対して正しい回答になっていないと議論全体の評価は大きく下がってしまいます。
ステップ⑧:発表する
結論を出すことができたら、あとは試験官に向かって発表するだけです。
発表のためにパワーポイントを作成する必要があるグループディスカッションもあれば、そうではないグループディスカッションもあります。
また発表時間も1分のもののあれば、3分のもののあるなどバラバラです。
ここはそれぞれのグループディスカッションの試験官が最初に言っていたことに従いましょう。
発表者になっても評価は上がらない
発表をすると評価が上がるなんてことが言われていますが、私はそんなことはないと思います。
理由は、発表の内容や話し合いへの姿勢を試験官は見ているのであって、発表者の自主性を見ているわけではないからです。
なので、私の場合は発表したい人がいない場合のみ、代表して発表していました。
グループディスカッションをうまく進めるコツ
wp-content/uploads/2022/03/s-34-1024x683.jpeg" alt="" class="wp-image-5310"/>
ここからはグループディスカッションをうまく進めるコツについて紹介します。
具体的には以下の4つを行うことをおすすめします。
- お題が出された時に自分の中で議論の筋道を立てておく
- 時間配分は余裕を見て行う
- 議論の最中に発表しやすいドキュメントにする
- 結論はできる限り1つにする
順番に解説します。
お題が出された時に自分の中で議論の筋道を立てておく
こちらはすごい細かいテクニックですが、おすすめ。
グループディスカッションではお題が共有されてから、議論時間の説明だったり、発表スタイルの説明だったりの時間があります。
また自己紹介の時間がある時もあるでしょう。
そういった時間の間に自分の中で議論の筋道を立てることをおすすめしています。
話し合いの前に議論の筋道を立てておくことで、議論の流れが見えやすくなり、議論の展開に合わせた発言ができるようになります。
お題の種類分けだけでもやっておくと◎
もし議論の筋道を立てるのが難しい場合でも、お題の種類について考え、テーマごとの議論の進め方を軽く見ておくだけでも議論がしやすくなります。
お題の種類とテーマごとの議論の進め方について知りたい人には以下の記事がおすすめです。
時間配分は余裕を見て行う
グループディスカッションでは議論が白熱するあまり、時間がなくなりやすいです。
私の所感では、9割近くのグループディスカッションでは時間が足りなくなっていました。
そこでおすすめなのが、余裕を持って時間配分を行うことです。
どういうことかと言うと、最後に3分くらいバッファを持っておくということです。
例えば…
例えば30分の議論時間の場合、
- 5分:前提確認
- 5分:現状分析
- 10分:施策検討
- 5分:発表資料作成
- 5分:バッファの時間
というような感じにするのがおすすめです。
私の意見としてグループディスカッションで時間が余ることは少ないので、余裕を持って議論を進めましょう。
議論の最中に発表しやすいドキュメントにする
議論の最中から発表しやすいドキュメントにするのがおすすめです。
どういうことかというと、議論が行われている間に綺麗に整理されたドキュメントにするということです。
そうすることで発表の前に発生する「このロジックどんなのだっけ?」という時間をなくすことができます。
wp-content/uploads/2022/10/cropped
ただしこのコツを実践できるのは書記である人だけなので、書記を普段やらない人は関係がないです。
結論はできる限り一つにする
グループディスカッションでよく発生するのが、案Aも案Bもいいから、どっちも採用しようとなることです。
これ自体は問題ではありませんが、グループディスカッションという場においては控えたほうがいいと思っています。
なぜかというと、施策の優先順位づけができていないということだからです。
例えば…
例えば、マクドナルドの売り上げを2倍にするお題だっとしましょう。
その際に「デザートの種類を増やすのと勉強しやすいように個室を用意して、そこは別料金発生するようにする」との結論が出たとします。
これだと、やるべき施策が絞り込めていません。
当たり前ですが、思いつく限りの施策を全て行えば、売上を2倍にするのは簡単です。
ただし実際のビジネスシーンでは、少ないリソースに対して、優先順位順に施策を行なっていく必要があります。
なので、結論を出す際には施策や案を優先順位付けし、最も優先順位が高かったものを結論とするようにしましょう。
グループディスカッションの事前準備
wp-content/uploads/2022/03/s-35.jpeg" alt="" class="wp-image-5311"/>
グループディスカッションにぶっつけ本番で挑むのはリスキーな選択だと思います。
なので、事前に少しは準備をしておくことがおすすめです。
グループディスカッションの事前準備としては、以下の3つを行うのが良いでしょう。
- 日常的にニュースをチェックする
- 自分ならどうするか考える
- グループディスカッションの練習をする
順番に解説します。
日常的にニュースをチェックする
グループディスカッションの原因分析や施策を立案するときに意外と大事になるのが、社会について知っていることです。
例えば「保育園の数を増やす方法を立案せよ」というグループディスカッションだっとしましょう。
そこで実はニュースにて「保育園設立の際の負担をカバーする助成金案が可決された」とします。
もしこの人がそのニュースのことを知らなくて「助成金を国が出す方法」が良さそうと結論を出すと、
「それってもう実際に行われることだよね?他に何か施策はありますか?」
となってしまいます。
wp-content/uploads/2022/10/cropped
そうなることを避けるためにも、日常的にニュースをチェックすることがおすすめです。
就活生が登録するべきニュースサイトは以下の記事で紹介しているので、ぜひ。
自分ならどうするか考える
常に周りの物事に対して自分ならどうするのか考えることも重要です。
例えばニュースで「〇〇株式会社が破産申請」などを見たときに、自分ならこうしたのにという自分の考えを持つといった感じです。
これをすることで、日頃から物事に対する自分の考えを持つようになります。
そしてそれがグループディスカッションで生きてくるというわけです。
グループディスカッションの練習をする
当たり前ですが、グループディスカッションの練習をすると、グループディスカッションの対策ができます。
グループディスカッションの練習方法は大きく分けると3つあります。
- グループディスカッションのLINEグループに参加
- 就活サロンに参加
- ケース面接の練習
上記の方法のうち、一番みなさんに合うものを使って練習をするのがおすすめです。
もし上記3つが何かわからない人は、以下の記事で具体的なグループディスカッションの練習方法を確認しましょう。
まとめ
ここまで記事を読んでいただき、誠にありがとうございます。
この記事を読んでくださったあなたは、グループディスカッションの流れへの理解度が深くなっていると思います。
このサイトでは他にもグループディスカッション関連の記事を公開しているので、気になる人は以下の記事から読んでみることをおすすめします。
-

-
小田楓
マーチ生だった楓です。月間1万人以上が訪れる「就活生だからこそ言えること」を伝えるサイト、就活備忘録.comを運営しています。22卒/長期インターン2社→ITベンチャーにて人事
人気の記事
-
 1
1
-
Fラン生こと逆求人使って欲しいんですが、話題の逆求人サイトってスカウトが来るって聞いたんだけど、なんか怪しいんだよな。 みたいな事を思ってる人も多いのでこういった疑問を解決します。 この記事を読むとわ ...
-
 2
2
-
私は23卒就活生でしたが、早期選考で某有名ITベンチャーから内定をもらい、就職活動を終えました。 就職活動自体は半年ほど行なったのですが、その中で自分が愛用していたサイトやサービスを今回はまとめていき ...
-グループディスカッション
-グループディスカッション