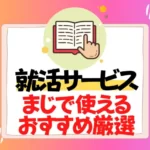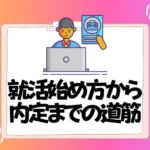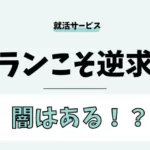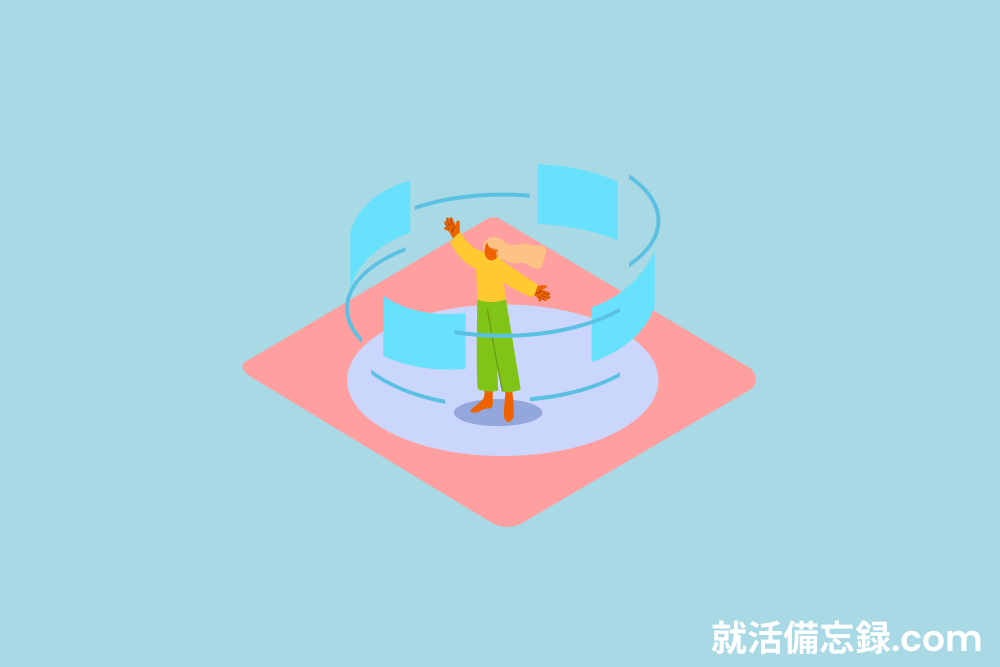
グループディスカッションの苦手を克服する方法4つと評価ポイント5つを解説します。
- グループディスカッションが苦手。どうやって通過するのかわからない。
- グループディスカッションの苦手を克服する方法が知りたい。
みなさんはこういった疑問をお持ちではないでしょうか?
この記事はそんなみなさんにぴったりの記事となっています。
この記事を読むとわかること
- グループディスカッションが苦手な人の特徴
- グループディスカッションの苦手を克服する方法
- グループディスカッションで評価されるポイント
- グループディスカッションの練習方法
私自身、グループディスカッションが特段得意だったわけではないですが、通過率は90%以上を維持することができました。
今回はグループディスカッションが苦手な人が苦手を克服し、グループディスカッションを通過できるように解説していきます!
グループディスカッションが苦手な人の特徴
グループディスカッションが苦手な人の特徴とはどんなものなのでしょうか?
具体的には以下の特徴が見受けられます。
- 一人で黙々と作業を進めるのが好きなマイペースな人
- 初対面の人と打ち解けるのが苦手な人
- 自分の発言に自信がない人
- 頭の回転が遅い人
一つずつ説明します。
一人で黙々と作業を進めるのが好きなマイペースな人
グループディスカッションは複数人数で議論をしていくという特徴があるため、自分のペースでゆっくり考えてから議論したい人にはなかなか難しいですよね。
私はこのタイプだった
実は私はこのタイプで、自分のペースで考えて、腑に落ちてから議論を進めたいと思っていた人間です。
なので、いつも「なんでこの人たちはその原因が一番大きな原因だと仮定して議論を進めているのだろう」と思っていました。
もし皆さんがグループディスカッションに苦手意識を持っている場合は、私と同じくマイペースに考えたいと思っている人かもしれません。
社会に出たら、じっくり自分で考えてから議論をするのが一般的
社会に出たら、自分の中で腹落ちするまでじっくり考えてからドキュメントにして、会議にてそれについて議論するのが一般的です。
なので、グループディスカッションができないからといって社会に出て困ることはほとんどないでしょう。
初対面の人と打ち解けるのが苦手な人
グループディスカッションは複数の初対面の人と打ち解けることにより、より良いアウトプットを出すことができます。
実際にみなさんも「会話が弾んだグループディスカッションはうまくいった」という経験があるのではないでしょうか?
ただ逆を言うと、なかなか空気が重いグループでのグループディスカッションは大抵の場合、良い結果が出ない場合が多いです。
そのため、自分から初対面の人と打ち解けてグループの空気を作れる人はグループディスカッションを得意としている傾向があります。
しかしながら、初対面の人と打ち解けるのが苦手な人はグループディスカッションを苦手としている傾向があることも事実です。
自分の発言に自信がない人
グループディスカッションは短時間で結論を出す必要があるため、時には自分の発言に自信を持って、ゴリ押しする必要もあります。
そこで自分の発言に自信がある人はそのまま議論を進めることができますが、自分の発言に自信がない人はそのまま議論をゴリ押すことが難しいでしょう。
また、自分の発言に自信がない人はそもそもの発言数も減ってしまい、グループディスカッション通過が難しくなってしまう場合もあるでしょう。
頭の回転が遅い人
頭の回転が遅い人もグループディスカッションを苦手に感じているでしょう。
なぜなら、自分のペースで議論が進んでいくわけではないからです。
グループディスカッションでは流れがある
グループディスカッションでは、お題ごとに最適な議論の流れがあります。
それを理解していれば、頭の回転が遅くてもグループディスカッションを通過できるようになるでしょう。
気になる人は以下の記事をチェックしてみましょう。
グループディスカッションの苦手を克服する方法
ここからはグループディスカッションを苦手と感じている就活生が苦手意識を克服する方法について紹介します。
以下の4つの方法を試すことで、苦手意識を大きく改善することができるでしょう。
- 自分の役割を見つける
- 自分でメモをとる
- 具体と抽象を行き来できるようにする
- 自分の発言に自信を持つ
一つずつ解説します。
自分の役割を見つける
皆さんが、グループディスカッションが苦手で通過できない理由の一つの「自分の存在価値を発揮できていない」という理由があるかもしれません。
どういうことかというと、その人がいてもいなくても議論の内容に差が出ないということです。
残念ですが、こういった判断が下されることはよくあります。
自分の役割を見つける
であるならば、自分の役割を見つけましょう。
例えば皆さんが議論をまとめるのが上手いのであればリーダー的な役割をやっても良いですし、メモを取るのが上手いのであれば書記でOKです。
もし何も得意なことがないならば、自分の存在によって議論の内容が変わったと断言できるような印象を議論の中で残しましょう。
グループディスカッションの役割について詳しく知りたい人は以下の記事を参考にしましょう。
自分でメモをとる
みなさんはグループディスカッションにて、今なんの話をしているのかわからなくなったことはありませんか?
私はよく「そもそもこの話ってなんで話し合う必要あるんだっけ?」となることがありました。
そこでおすすめなのが、書記のメモとは別に自分でもメモを取る方法です。
自分で自分なりの方法で論点を整理しながらメモを取ることで、無駄な議論をしなくて済むようになります。
また、議論についていきやすくなります。
なので、自分なりのルールで自分用のメモを取ることをおすすめします。
具体と抽象を行き来できるようにする
こちらは少し難しいですが、できるようになるとグループディスカッションの通過率を大幅に上げることができます。
具体と抽象の行き来とはどういうことか分かりにくいと思うので例文を使って説明します。
例えば…
例えば、お題が「新宿にあるラーメン屋の売り上げを2倍にしてください」だとします。
そしてどんな施策にするかとして「セットメニューの内容変更や価格変更」について話しているとします。(これは具体です)
そうすると、ここでの抽象とは「メニューの変更」となります。
イメージとしてはメニューの変更という施策の中に「セットメニューの価格変更や内容変更」があるということです。
この具体と抽象を行き来する思考ができるようになると、今話している内容が何に紐づくのかわかるようになり、議論が脱線しないようになります。
具体と抽象の思考法を鍛える方法
具体と抽象に関しては、以下の本を参考にすると、思考法を鍛えることができます。
もし気になった人はチェックしてみてください。
自分の発言に自信を持つ
自分の発言に自信を持つことも苦手意識を克服するためには大事です。
少し脱線しますが、あのメンタルおばけで有名なサッカーの長友選手でさえ、メンタルが弱っていた時はパフォーマンスが出せなかったといっています。
なので、自分に自信を持つことはより良いパフォーマンスを出すために必須です。
自分の発言に自信を持つ方法として、グループディスカッションの練習をすることが挙げられます。
練習をたくさんすることで、グループディスカッションに慣れることができ、自信を持てるようになるでしょう。
グループディスカッションの練習方法は後ほど解説します。
グループディスカッションの評価ポイント
ここからはグループディスカッションで評価されるポイントを紹介します。
以下のポイントを面接官は見ている可能性が高いです。
- コミュニケーション能力
- 協調性
- 論理的思考力
- 発想力
- まとめる力
順番に解説します。
コミュニケーション能力
一対一のコミュニケーション能力を見たいのであれば、面接でも見れますよね。
グループディスカッションを通じて見ているコミュニケーション能力は、チームメンバーとのコミュニケーション能力です。
仕事はチームで行う
仕事は一人で進めることはほぼなく、誰かしらと連携をしながら進めていきます。
そのときにどのようにチームメイトに接するのかをグループディスカッションを通じて見ているのです。
協調性
グループディスカッションをする際に評価するポイントの2つ目が協調性です。
もし仮に他の人がトンチンカンな発言をしても、否定的にならず、その発言に対して優しく接することができているかなどを見ています。
大事なのは否定から入るのではなく、「確かにそうですね、ですが」のような肯定から入ることです。
また周りと自分の意見が一致しているときは賛同をしっかりするのかなども見られています。
私はこれを知らずに最初のグルディスに落ちた
インターンをやっていたり、ディスカッションに慣れている人ほど「自分の言っていることが正しい」と思いがちです。
決して自分の言っていることが正しいと思い込まず、相手の意見も聞くようにしましょう。
論理的思考能力
グループディスカッションは「お題についてみんなで話し合い、結論を出す」選考です。
基本的に結論の鋭さやアイデアの新規性などはそこまで問われません。
大事なのは、その結論に至る過程で、どのような論理が組まれたかです。
例えば…
お題が「赤い果物は?」だとします。
出た結論が、「りんご」だとします。
面接官が「なぜりんごとしたのですか?」と聞いた時に、「それが唯一の赤い果物だからです」と答えてはダメですね。
なぜなら「イチゴ」も赤い果物だからです。
このように「漏れなくダブりなく」考えることが大事です。
ちなみにこの「漏れなくダブりなく」の考え方は、MECEと呼ばれていて、コンサル業界などでは多用されているフレームワークです。
発想力
グループディスカッションでは、発想力が求められる瞬間が多いです。
例えば「幸せな人とはどんな人?」というお題だとすれば、幸せな人はどんな人か考える必要があります。
そのときにたくさんアイデアを出せる人は議論を前に進めることができ、良い評価を得ることができます。
グループディスカッションでは限られた時間内で結論を出す必要があるため、発想力が鍵になることもあります。
まとめる力
議論をまとめる力も大きく評価されるポイントの一つです。
グループディスカッションは初対面の人たちが時間内に結論を導くためにさまざまな議論をします。
その結果、議論の内容が本質とは関係ないところに行ってしまうこともありますよね。
そうなってしまっては議論をしている意味がありません。
そこで議論を修正して、まとめる力がある人がいると議論が元の方向に戻ります。
なので、議論をまとめる力がある人も評価されます。
グループディスカッションを通過するコツが知りたい
そういった人は以下の記事にてグループディスカッションのお題ごとに通過するコツを解説しているので、チェックしてみてください。
グループディスカッションの練習方法
グループディスカッションの練習方法を早速解説します。
具体的には以下の3つの練習方法があります。
- グループディスカッションのLINEグループに参加
- 就活サロンに参加
- ケース面接の練習
順番に解説していきます。
グループディスカッションのLINEグループに参加
当たり前ですが、グループディスカッションは複数人が集まらないとできないですよね。
最低でも3人は必要です。
でもなかなか3人以上を集めてグループディスカッションをできる人は多くないでしょう。
そんな時におすすめなのが、LINEのオープンチャット機能を使ったグループに参加することです。
論より証拠だと思うので
以下が私が参加していたグループディスカッションのオープンチャットグループです。
こんな感じで、グループに参加している人たちが自分たちでグループディスカッションを開催し、グループ内で参加メンバーを募集しています。
募集もかなり多く、グループ自体もたくさんあるのでグループディスカッションの練習をしたいなら、LINEのオープンチャットを使うのが良いでしょう。
オープンチャットをLINEで開いて、検索窓に「グルディス」とか「グループディスカッション」とか入れて検索すれば該当のものがたくさん出てくるので、参加してみましょう。
具体的な参加方法
慣れないうちは募集を見つけて、そこに声をかける形で参加するようにしましょう。
募集している人がいたら、日にちと時刻を確認し、参加できる場合は「参加希望です。まだ空いていますか?」などとメッセージを送りましょう。
もし空いている場合は、当日の10分前くらいからオープンチャットに張り付き、Zoomのリンクが送られてくるのを待って、送られてきたら参加すればOKです。
オープンチャットは匿名で行われているため、他の人があなたのフリをして参加しようとする場合もあるので、なるべく早めにZoomの部屋に参加することをおすすめします。
オープンチャットは他にも
ちなみに、LINEのオープンチャットで就活関連で参加するべきものとして、unistyleのオープンチャットもあります。
詳しく知りたい人は以下の記事をチェックです。
就活サロンに参加
就活サロンに参加して、グループディスカッションの練習をするのもグループディスカッションの練習方法としてありです。
wp-content/uploads/2021/06/IMG_6333-2-1.jpg"/>かくいう私も就活サロンに参加して、グループディスカッションの練習をしたことがあります。