今度プレゼン面接があるのですが、資料はどのように作ればいいのでしょうか?
また、プレゼンのコツが知りたいです。

プレゼン面接とは名前の通り、プレゼンをする面接のことを言います。
近年は面接に関する情報がありふれているため、面接だけでは就活生の本当の実力を測れない場合があります。
なので、プレゼン面接を行い、就活生の本当の実力を測ろうとする企業が増えています。
プレゼン面接のテーマ
プレゼン面接では主に以下のようなテーマがあります。
ほとんどの場合、事前にプレゼン資料を用意し、モニターに移しながら発表といった形が取られます。
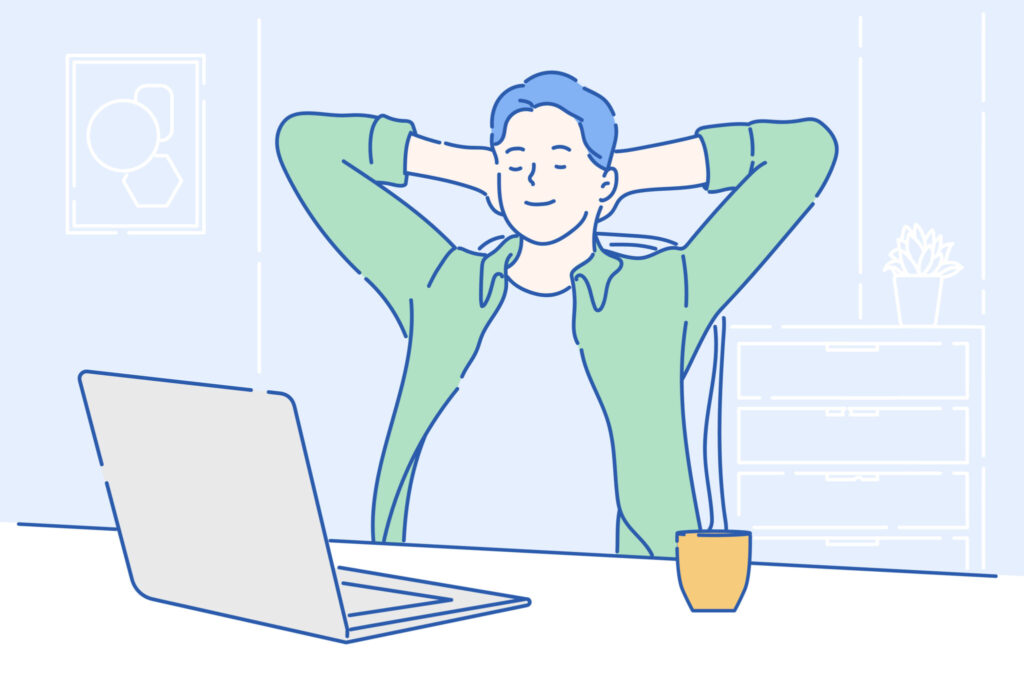
プレゼン面接は一般的な口頭でのコミュニケーションをとる面接とは違いますよね。
企業はなぜプレゼン面接を実施するのでしょうか?
結論、就活生の本当の実力を見るためです。
情報が溢れている
近年の就活は情報過多になっており、学生が簡単に対策をできるようになっています。
例えば、ワンキャリアやユニスタイルのようなサイトを使うことで、過去に聞かれた質問や選考を通過したESなどが見れます。
そうすると、面接では用意された答えを聞くだけになってしまい、就活生の本当の実力が分かりません。
なので、企業はプレゼン面接を実施し、コミュニケーション能力や論理的思考力を見たいのです。
プレゼン面接には色が出る
また、プレゼン面接は資料作成やプレゼンスタイルなど、面接と違って色が出やすいです。
企業としてはその就活生の本当の姿を知りたいので、プレゼン面接はもってこいというのも背景としてあります。
新卒なので、どんな人なのかが大事になります。
それが見れるのがプレゼン面接ということです。

プレゼン面接ではどのような観点で評価されるのでしょうか?
以下、プレゼン面接で評価される観点です。
順番に説明します。
当たり前ですが、まずはプレゼンテーション能力は企業から見られています。
プレゼンテーション能力とは、分かりやすく、自分の伝えたいことを伝える能力です。
社会人になると、他社に営業をかけるときに自社のサービスをプレゼンしたり、社内で今後の方針をプレゼンすることが多々あります。
特に営業職の人は営業先に出向いて、日常的に自社のサービスをプレゼンすることになるでしょう。
このようにプレゼンテーションは社会人になると日常的に行われることなので、その素養があるのか、確認しています。
資料を用意して行うプレゼンではなくても、大勢の前で経理の話をしたりすることはあるはずです。
自己表現力とは、別の言葉で言うと「オリジナリティ」です。
どれだけ「自分を持っているか、個を持っているか」と言うことになります。
自己表現力はプレゼンで使う資料の色や構成、プレゼンでの話し方などから推測することができます。
自己表現力がある人だと、他の人を引っ張っていけるリーダーになれたり、スーパー営業マンになれたりします。
なので、自己表現力も重要であるということです。
いわゆるカリスマも、自己表現力のある人ですよね。
プレゼンテーションは初めから終わりまでのつながりが大事です。
ということは、論理的に流れを組み立てる能力が必要となります。
論理的思考能力は会社に入ったら必ず使う能力です。
なので、その素養があるのかをプレゼンテーションを通じて見ているということです。
論理的思考能力とは、プレゼンの流れを組み立てるだけではなく、他の人にうまく伝えるための構造化なども含まれます。
この人説明うまいな〜という人は大体、構造化が上手い人だと言えますね。
私的には中田敦彦とかその典型例な気がしています。
自分が思っていることを伝えるためには、資料を使いながら口頭で説明するのが良いですよね。
伝わりやすい、良い資料を作れる人は、コミュニケーションを円滑に進めることができるので、会社としても欲しい人材です。
資料作成は社内、社外問わずにいつでも必要なアクションです。
そんな資料作成スキルがあるのかどうかをプレゼン面接では見ています。
プレゼンにおける良い資料とはデザインが凝っている資料ではありません。
相手に伝わる資料が良い資料です。なぜなら、プレゼンは相手に伝えるのが目的なので。

ここまで読んで、
結局、プレゼン資料も大事なんでしょ?
作り方を教えてよ!
と思った人もいるでしょう。
なので、今からプレゼン資料を作る際のポイントを紹介します。
一つずつ紹介します。
プレゼンとは、相手に伝えるために行うためで、自分が言いたいことを言う機会ではありません。
これはめちゃめちゃ大事な考え方で、良いプレゼンとは「相手に伝わり、相手が動いてくれるプレゼン」です。
なので、まずは相手に何を伝えたいのか、そしてそれを聞いた相手をどのように動かしたいのか決めましょう。
伝えたいことは一つか二つにしましょう。多くを伝えようとすると、聞き手は混乱してしまうからです。
プレゼンが上手い人はよく「キーメッセージ」のスライドを作っている印象がありますね。
よくあるミスが「文字が小さすぎて、読みづらい」です。
プレゼンを作っている人は見やすい大きさで作っているつもりでも、実際に投影するモニターでは小さく写ってしまうことはあるあるです。
プレゼンでは基本的に文字はできるだけ大きくするのが良いでしょう。
また、フォントも凝ったものにする必要はなく、デフォルトのフォントや学校の教科書に似ているフォントを選ぶようにしましょう。
フォントも字の大きさも「伝えたい相手のこと」を考えれば、大きくて分かりやすいものにするべきとなるはずです。
プレゼン資料で使うべき色の数は3色と言われています。
黒と白、それとアクセントカラー1色が良いです。
そんな資料、デザインがなくてつまらないでしょ!
と感じる人もいるでしょう。
ここで思い出してほしいのが「プレゼンの目的」です。
プレゼンは「相手に伝えたいことを伝え、動いてもらう」のが目的です。
なので、「デザインはできるだけシンプルに分かりやすく」が鉄則なんです。
伝えたいことを明確にするのと自然とできてしまうのですが、情報を絞ることも重要です。
経験ある人もいると思いますが、1ページに含まれる情報量が多いプレゼン資料は見ている側が疲れてしまいます。
見ている側が疲れるということは、伝えたいことを伝えられない可能性が高くなってしまうということです。
これではプレゼンの目的を達成することはできません。
なので、できるだけ見ている人を疲れさせないように資料作りをすることも重要となります。
そうすると、自然と情報を絞って資料に組み込むことができるようになるはずです。
ここまで読んでいただき、ありがとうございます。
プレゼン面接は近年の就活で増えてきている面接です。
ただ、まだまだ浸透はしていないので、差がつくポイントでもあります。
なのでこの記事の内容を活かして、プレゼン面接での資料作成などがうまくいくことを願っています。
この記事の読者には以下の記事がおすすめです。
人気の記事
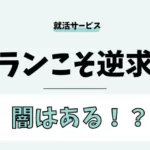 1
1
Fラン生こと逆求人使って欲しいんですが、話題の逆求人サイトってスカウトが来るって聞いたんだけど、なんか怪しいんだよな。 みたいな事を思ってる人も多いのでこういった疑問を解決します。 この記事を読むとわ ...
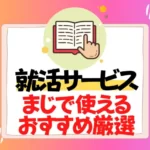 2
2
私は23卒就活生でしたが、早期選考で某有名ITベンチャーから内定をもらい、就職活動を終えました。 就職活動自体は半年ほど行なったのですが、その中で自分が愛用していたサイトやサービスを今回はまとめていき ...