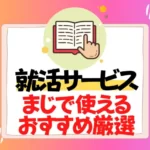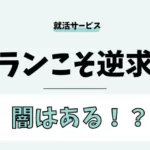就活に失敗しても大丈夫です。4つのステップでやることを解説。【大事なのは入社後に得られるスキル】
みなさんはこういった疑問をお持ちではないでしょうか?
この記事はそんなみなさんにぴったりの記事となっています。
この記事を読むとわかること
- 就活を失敗しても大丈夫な理由3つ
- 就活を失敗した人がするべきこと
- 就活にこだわる必要はない
- これからはスキルが大事な社会
結論、就活に失敗することを恐れる必要は全くありません。
早速詳しく解説していきます。
就活は失敗しても大丈夫です
繰り返しの結論ですが、就活に失敗しても問題はありません。
理由は以下の通りです。
- ①:大学を卒業している限り、多くの企業に応募できる資格がある
- ②:第二新卒での応募が当たり前になっている
- ③:就職先で自分がどれくらい頑張れるかが大事
順番に説明します。
①:大学を卒業している限り、多くの企業に応募できる資格がある
多くの企業は大卒と高卒以下で、入社への壁を作っているパターンがほとんどです。
そのため、大学卒業という資格を取ってさえいれば、後からいくらでも企業の選考に応募することができます。
もし仮に就活で失敗したとしても大学卒業の資格があれば、後からやり直すことができるということです。
②:第二新卒での応募が当たり前になっている
近年では転職が当たり前になってきていますね。
それに伴って、第二新卒での応募がかなり当たり前になってきています。
転職サイトの求人を見ても、「第二新卒歓迎」という文字をよく見かけます。
なので、就活で失敗したとしても第二新卒として希望する業界や会社に入れる可能性は今までよりも高いです。
後ほど詳しく説明しますが、就活が全てではないので、就活に失敗したと思っている人は第二新卒からやり直しを図りましょう。
③:就職先で自分がどれくらい頑張れるかが大事
就職先が大事か大事ではないかと聞かれると、私は大事ではあると思います。
それは「スキル」がつけられるかそうではないかが大事だからです。
ただ、一番大事なのは就職先で自分がどのくらい頑張れるかが大事になります。
仮にいわゆる就職偏差値が高い企業に入れたとしても、そこで真面目に働かず、スキルを身につけることができなければ意味がありません。
大手企業に入っても「窓際族」になって、他社では全く価値がない人が大手企業にもいることが物語っているでしょう。
就活を失敗した人がするべきことを解説
ここからは就活に失敗した人がするべきことを解説します。
具体的には以下の手順を行うことをおすすめします。
- ステップ1:もう一度就活をするのか決める
- ステップ2:もう一度就活をしないなら、今の就活をどうするか決める
- ステップ3:内定をもらっている企業に就職するのか決める
- ステップ4:内定先で働くまでに何をするのか決める
このままだと具体的に何をすればいいのかわからないと思うので、さらに詳しく説明していきます。
ステップ1:もう一度就活をするのか決める
就活に失敗した場合は、まずは「もう一度就活をするのか」というのを決めましょう。
- 大学を休学して、あえて卒業せずにもう一度就活をするのか
- それとも今の就活を続けて少しでも希望の企業に入るのか
ここら辺が分かれ道になるところです。
ちなみにもう一度就活をしたい場合は、大学を休学して卒業しないようにしなくてはいけません。
詳しいことは以下の記事にて解説しています。
もう一度就活をすると決めた人はこの先を読む必要はありません。
2回目の就活を成功させるために「1回目の就活で何が足りなかったのか」を考えるようにしましょう。
ステップ2:もう一度就活をしないなら、今の就活をどうするか決める
もう一度就活をしないと決めた皆さんは、今の就活をどうするのか決める必要があります。
- 現状内定をもらっている企業に内定承諾をするのか
- それとも、より良い企業から内定をもらえることを考えて就活を続けるのか
ここら辺が論点となります。
もしみなさんが内定をもらっている企業に少しでも「不安」を感じてみたら、一度就活を続けてみても良いかもしれません。
他の企業を見てみると、内定をもらっている企業の良さに気づいたり、逆に良くないところに気づいたりすることができるからです。
ステップ3:内定をもらっている企業に就職するのか決める
ステップ3では、内定をもらっている企業に就職するのか決めましょう。
私は基本的には、就職する場所はあまり関係ないと思っているので、せっかく内定をもらっているのであればそのまま内定を承諾することをおすすめします。
従業員数10名程度の町工場などでは再考の余地はありそうですが、一般的な中小企業であるならば、就職しても全く問題はないと思っています。
ステップ4:内定先で働くまでに何をするのか決める
内定を承諾した人は、内定先で働くまでに何をするのか決めましょう。
例えばインターンをしてみたり、プログラミングを始めてみたりなどがおすすめです。
後ほど詳しく説明しますが、これからは「スキルをベースとした社会」になっていくと想定されています。
そのため、入社前からスキルの向上を図っておくことは自分の保身になります。
私の例を出すと、私はこのブログとインターンに卒業までの時間を割くことを決めました。
理由は「スキルが付くと考えたから」です。
なので、みなさんにも何か自分の元に「資産」が残る体験を卒業まで行うことをおすすめします。
就活にこだわる必要はなし
こちらは私の意見ですが、就活にこだわる必要はないです。
就活に失敗したからといって死ぬわけではないですし、生きていけないわけではありません。
世の中では高卒や中卒で、就活なんてものを知らない人だってたくさんいます。
なので、就活にこだわる必要はないんです。
フリーランスやフリーターも選択肢の一つです
就活をしているとどうしても「企業に就職する」というのが既定路線のようになってしまいますが、フリーランスやフリーターなどの個人事業主も選択肢として持っておくと良いでしょう。
企業に就職して働くことが最適解ではありません。
もし皆さんの中で、自分が働きたいと思った時に働きたいという思考を持っている人がいたら、フリーターやフリーランスとして働くのがおすすめです。
私自身も将来的にはフリーランスのような形で、自分一人で生きていけるようになりたいなと思っています。
自己分析をやり直そう
自分が就職するべきなのか、それとも独立してやっていくべきなのかは「自己分析」をすることでわかります。
なので、自己分析をやり直すことをおすすめします。
自己分析のやり方がわからない人は以下の記事を参考にすることで、効率よく自己分析を進めることができるのでぜひ。
自己分析の結果、私はさまざまな土地で働きたいことがわかったため、自分にスキルという資産をつける必要があることがわかり、ベンチャー企業で働くことを決めました。
これからはスキルが大事な社会です
さて、先ほどから何回か説明していますが、これからはスキルが大事な社会となります。
それを裏付けるのが「人材の流動性」の増加です。
これだけだと何をいってるのかわからないと思うので詳しく説明していきます。
転職の求人が増えている
みなさんもご存知だと思いますが、転職の求人は今までよりも増加傾向にあります。
就活生でも「転職」を前提とした就活をしている人も多く見られます。
この転職の求人が増えている状況を難しい言葉で説明したのが、人材の流動性が増えているという状況です。
転職の求人が増えている→転職する人が増える→人材の流動性が増える
という形です。
スポット採用が増える
人材の流動性が増えると何が起こるかというと、スポット採用が増えます。
スポット採用とは、その場で必要な人材をそのタスクにだけ採用するという採用方法です。
いわゆるアウトソーシングに近いイメージですね。
例えば、デジタルマーケティングの専門的な人材がプロジェクトに欲しいとなったときに、そのプロジェクトだけのために短期間だけ採用するといった感じです。
人材の流動性が上がると、市場に求職をしている人材が増えるため、こういった採用方法を取ることができるようになります。
もちろんこの方法は企業からすると人件費削減に繋がるため、企業からしたらメリットが多い方法となります。
スキルがないとスポット採用に対応できない
当たり前ですが、スポット採用ではその職種の専門家が採用されやすいです。
未経験の人をゆっくり育てている時間はないですからね。
なので、スキルがない人は今後の流動性が上がる市場に対応できなくなります。
ということで、スキルを身につけるのが大事ということです。
もちろん大企業に入ってジョブローテーションなどを繰り返しながら、社内での立ち位置を確立していくことで定年を迎えるという方法を取ることもできます。
ですが、その企業が潰れてしまうことだってあり得ます。
そうなった時に自分の身を守れるのは自分だけです。
こういった理由もあって、私は大企業に就職することをあまりおすすめしていません。
今後のキャリアについて考えたい人へ
私は就活中、キャリア論の多くを「北野唯我」さんの本から学びました。
気になる人がいたらまずはぜひ以下の本から読んでみることで、自分が辿るべきキャリアが見えてくるかもしれません。
まとめ
ここまで記事を読んでいただき、ありがとうございます。
最後は就活に失敗というメイントピックから少しずれてしまったように感じます。
ですが、就活とキャリアは密接に関わっているものなので、少しはキャリアについて考えてみることをおすすめします。
一応以下におすすめの就活系記事を載せておくので、気になる人はサクッと読んでみても良いかもしれません。