
グループディスカッションの評価基準5つを解説します。【多分当たり前】
グループディスカッションでは、どんな評価軸で評価されるのですか?
こういった疑問を解決します。
この記事を読むとわかること
- グループディスカッションで最も大事なこと
- グループディスカッションの評価基準
- グループディスカッションの役割による評価
- グループディスカッションのアウトプットの評価
- グループディスカッションにて気をつけるべきこと
早速、解説していきます。

グループディスカッションでは、どんな評価軸で評価されるのですか?
こういった疑問を解決します。
この記事を読むとわかること
早速、解説していきます。
グループディスカッションにはさまざまな評価軸がありますが、何よりも大事なことが一つあります。
それは、チームとしてのアウトプットを出すのにどれだけ貢献できたかです。
チームとしてのアウトプットを高めるために誰もやりたくなかった書記を率先してやった。
これはチームのアウトプットを高めるために行動しているので「高評価」です。
逆に自分の意見を通したいから他人の意見を否定する。
これはチームとしてのアウトプットを高めているわけではないので、評価は高くありません。
wp-content/uploads/2022/10/croppedこのようにグループディスカッションでは「チームとしてのアウトプットを高めるためにどれくらい貢献したか」という大きな評価軸があるのです。
なぜチームとしてのアウトプットが大事?
そもそもなぜチームとしてのアウトプットが大事なのでしょうか?
具体的には以下の2つの理由から、チームとしてのアウトプットが重要視されています。
特に2つ目の項目は大事です。
実際に社会に出ると、一人で完結する仕事はほぼありません。
多くの人と関わり合いながら仕事をしていくので、他人と協調性を持って結論まで向かうことができる人なのかは重要な指標になります。
ここからはグループディスカッションで評価されるポイントを紹介します。
以下のポイントを面接官は見ている可能性が高いです。
順番に解説します。
一対一のコミュニケーション能力を見たいのであれば、面接でも見れます。
なので、グループディスカッションを通じて見ているコミュニケーション能力は、チームメンバーとのコミュニケーション能力です。
仕事は一人で進めることはほぼなく、誰かしらと連携をしながら進めていきます。
そのときにどのようにステークホルダー(関係者)に接するのかをグループディスカッションを通じて見ているのです。
wp-content/uploads/2022/10/cropped多少能力が低くても、コミュニケーションをとって、周りを巻き込んでいける人は強いです。
グループディスカッションをする際に評価するポイントの2つ目が協調性です。
もし仮に他の人がトンチンカンな発言をしても、否定的にならず、その発言に対して優しく接することができているかなどを見ています。
協調性を見せるために大事なのは、否定から入るのではなく、「確かにそうですね、ですが」のような肯定から入ることです。
また、「周りと自分の意見が一致しているときは賛同をしっかりするのか」なども見られています。
グループディスカッションは「お題についてみんなで話し合い、結論を出す」選考です。
基本的に結論の鋭さやアイデアの新規性などはそこまで問われません。
大事なのは、その結論に至る過程で、どのような論理が組まれたかです。
例えば…
お題が「赤い果物は?」だとします。
出た結論が、「りんご」だとします。
面接官が「なぜりんごとしたのですか?」と聞いた時に、
「それが唯一の赤い果物だからです」と答えてはダメですね。
なぜなら「イチゴ」も赤い果物だからです。
これでは、論理的に構造的に考えられていないため、高い評価をもらうことは厳しいです。
この「漏れなくダブりなく」の考え方は、MECEと呼ばれていて、コンサル業界などでは多用されているフレームワークです。
ぜひ覚えて、グループディスカッションで使いましょう。
グループディスカッションでは、発想力が求められる瞬間が多いです。
例えば「幸せな人とはどんな人?」というお題だとすれば、幸せな人はどんな人か考える必要があります。
そのときにたくさんアイデアを出せる人は議論を前に進めることができ、良い評価を得ることができます。
グループディスカッションでは限られた時間内で結論を出す必要があるため、発想力が鍵になることもあります。
議論をまとめる力も大きく評価されるポイントの一つです。
グループディスカッションは初対面の人たちが時間内に結論を導くためにさまざまな議論をします。
その結果、議論の内容が本質とは関係ないところに行ってしまうこともあります。
そうなってしまっては議論をしている意味がありません。
そこで議論を修正して、まとめる力がある人がいると議論がまっすぐ進みます。
なので、議論をまとめる力がある人も評価されます。
グループディスカッションでは、リーダーや書記、タイムキーパーなどの役割がありますよね。
では、この役割は評価対象なのでしょうか?
結論を言うと、役割の有無で評価が変わることはありません。
つまり、
ということです。
役割は引き受けなくていい
個人的には、役割は引き受けない方が良いと思っています。
なぜなら、役割があるとどうしても「その役割を遂行できているのか」という観点で見られることが多いからです。
例えば、書記の人がメモを取るのができていなかった場合、この書記の評価は下がってしまうでしょう。
しかしながら何も役割がない人が書記の仕事を代わりにやるくらいメモを取っていたとすると、この人の評価は上がるでしょう。
このように何も役割がない人が何かプラスアルファでやるというのが、もともとやらなくて良いものをやっているという積極性になり、高評価につながります。
wp-content/uploads/2022/10/croppedバイトとかで元々シフト入っている日に出勤しても何も言われないのに、急遽誰かにの代わりにシフトインしたら褒められるみたいな感じです。
せこいですが、こういう心理学を使って、専攻を有利に進めるのも大事なことです。
以下の記事にて、グループディスカッションの役割について解説しています。
役割ごとの評価ポイントについても解説しているのでぜひ。
議論の結果として出るアウトプットの質は評価されるのでしょうか?
結論を言うと、アウトプットの質は評価されます。
理由は以下の通りです。
順番に説明します。
グループディスカッション選考は選考フローの最初の方に出てきます。
なので、何十組ものグループが同じお題について議論します。
では、グループごとの良し悪しを決めるには何を軸に判断すればいいでしょうか?
結論としては、アウトプットの質になります。
アウトプットの質が高いグループはうまく議論ができているグループとなり、グループとして高い評価を受けることができます。
そして肌感覚的には、良いアウトプットが出ているグループディスカッションはグループ全体としての通過率が高いように感じました。
グループディスカッションの目的はアウトプットを出すことです。
当たり前のようですが、意外とわかっている人が少ないです。
というのも、就活生の多くがグループディスカッションの目的を「自分の能力を見せるため」とか「自分の論理的思考力を見せるため」だと勘違いしています。
グループディスカッションを行う目的はアウトプットを出すこと、すなわちアウトプットの質は大事なのです。
ここからはグループディスカッションで気をつけるべきことを紹介します。
具体的には以下の2つの点に気をつけることをおすすめします。
順番に説明します。
就活生はよく「今回のグループディスカッションではたくさん発言したから多分通過しているな」と思っている人が多い印象を受けます。
ただ、発言の回数が多いからといって評価されることは少ないです。
大抵の場合は発言の内容も加味された上での評価となります。
例えば、新商品としてスマホを売り出すにあたって搭載するべき機能はどんな機能かという話し合いをしているとします。
「このスマホはデザインがいけてないからデザインをもっといいものにする」という発言があったとしましょう。
これはマイナス評価な発言です。
なぜなら、お題の意図にあっていない発言だからです。
逆にいうと、お題にあっている発言で、グループとしてのアウトプットにインパクトがある発言の場合は高評価です。
私が就活生の時に耳にした都市伝説ですが、とある日系大手企業のグループディスカッションでは黙ってニコニコしているだけで通過することができるという噂がありました。
正直なことを言うと、これは嘘だと思っています。
なぜなら、黙って同調しているだけの人を次の選考ステップに通す必要がないからです。
みなさんが試験官だったらという仮定で考えて欲しいのですが、同調しているだけの就活生を次の選考ステップに通そうと思いますか?
おそらくそんなことはないと思います。
なので、グループディスカッションに参加した際には黙って同調するだけの地蔵にはならないようしましょう。
今回はグループディスカッションの評価について説明しました。
このサイトでは他にもグループディスカッション関連の情報を公開しているので気になる人はぜひ以下の記事からチェックしてみてください。
人気の記事
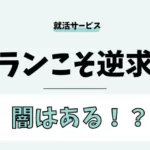 1
1
Fラン生こと逆求人使って欲しいんですが、話題の逆求人サイトってスカウトが来るって聞いたんだけど、なんか怪しいんだよな。 みたいな事を思ってる人も多いのでこういった疑問を解決します。 この記事を読むとわ ...
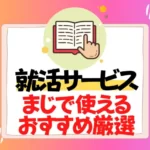 2
2
私は23卒就活生でしたが、早期選考で某有名ITベンチャーから内定をもらい、就職活動を終えました。 就職活動自体は半年ほど行なったのですが、その中で自分が愛用していたサイトやサービスを今回はまとめていき ...