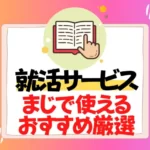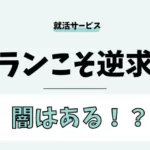グループディスカッションのコツってありますか?
効率よくグルディスを通過したいです。
こういった疑問を解決します。
この記事を読むとわかること
- グループディスカッションのコツ
- グループディスカッションのお題の種類とその進め方
- グループディスカッションを行う理由
- グループディスカッションでの役割
- グループディスカッションで評価ポイント
- グループディスカッションで気をつけること
この記事を読めば「グループディスカッションのコツや評価ポイント」などが分かります。
全て詰め込んだ結果、9000字を超える記事となっていますが、最後まで読んでもらえると嬉しいです。
グループディスカッションとは
グループディスカッションとは、グループになって、与えられたお題への結論を時間内に出すというのが一般的な解釈です。
お題としては、
「スターバックスが売上を2倍にするにはどうすればいいのか?」
などのビジネス的なものから、
「ストレスの解消法としてベストなものとは?」
などの抽象的なものまであります。
通常は5人程度のグループでディスカッションをして、結論まで導いていく形になります。
議論のアウトプットを見ているわけではない
就活生でよくあるのが、「グループディスカッションは議論のアウトプットが一番大事だ」という勘違いです。
私はグループディスカッションでは、「周りの就活生とどのように協力し、アウトプットまで持っていくのか」が重要だと思っています。
なぜなら、アウトプットが一番大事なら「グループでやる必要がない」からです。
グループディスカッションの評価についてもっと知りたい人は以下の記事を参考にすると良いでしょう。
グループディスカッションのコツを解説

ここからはグループディスカッションのコツを解説します。
コツを理解して、効率よくグループディスカッションを通過しましょう。
グルディスのコツは以下の通りです。
- 前提を定義する
- 実現可能なアイデアか見極める
- データを根拠に解答する
- 公平な視点から判断する
順番に解説します。
前提を定義する
グループディスカッションでは、抽象的なお題が振られることが多いです。
例えば、「マクドナルドの売上を2倍にするにはどうするべきか?」といった感じです。
上記のお題、人によって考えることが違うと思います。
私は都内に住んでいるので、都内のマクドナルド、もっと狭めると渋谷のマクドナルドを想定します。
しかし、アメリカに住んでいる人はアメリカのマクドナルドを想定します。
これでは、議論が進展するはずがありません。
なぜなら、そもそも議論以前に前提が違うからです。
なので、グルディスでは「前提の定義づけ」を必ず、実行するようにしましょう。
ちなみに、これをするだけでグルディスができる風を醸し出せるので、おすすめです。
実現可能なアイデアか見極める
グループディスカッションでは、その後に「思いついたアイデアを実行する」というステップがないです。
そのため、実現可能ではないアイデアを結論として出す人がいます。
アイデアの立案後のアクションというステップこそないものの、グループディスカッションはあくまでも、実際に行われる議論に近しいものです。
なので、実現可能なアイデアを出す必要があります。
ということで、議論しているアイデアが「そもそも実現可能なのか」という観点をグルディス中に持っておくと、評価が上がります。
データを根拠に解答する
グループディスカッションでよくあるのが、全員の憶測で話が進んでいくことです。
このターゲット層の人はおそらくこれを求めているから、こうだよね
みたいな感じで、憶測の上に憶測を重ねることをしがちです。
私も就活生の時によくやっていました。
できれば、データを用いて議論を進めるのがベターです。
例えば、40代の未婚女性は月収の2割を美容に使っているから、ここをターゲットにするべきなどが言えます。
ただ、時間がない中でデータを抽出して、整理するのは無理だと思うので、あくまでも「できたらベター」という認識で大丈夫です。
公平な視点から判断する
グループディスカッションはバイアスがかかります。
自分の中で「この案は良いアイデアだ」と思うと、そっちに議論を持っていきたくなります。
また、自分が興味関心がある方向に議論を持っていきたくもなります。
グループディスカッションのゴールは、グループとしてベストな議論をして、ベストな解答を出すことです。
なので、できるだけ公平な視点から議論を判断し、進めるようにしましょう。
あまりにも自分の進めたい方向に議論を進めると、「自己中心的」と捉えられ、評価が低くなります。
グループディスカッションのお題の種類

グループディスカッションでは初見のお題が出されるものの、出されるお題は3つの種類に分けることができます。
その3つとは以下の3つです。
- 課題解決型
- 二者択一型
- 自由討論型
一つずつ説明していきます。
課題解決型
課題解決型とは以下のような質問のことを言います。
- 吉野家が売り上げを伸ばすためには?
- マクドナルドの売り上げを伸ばすためには?
- 高齢者にiPhoneを普及させるには?
- 地方に移住する人を20%増加させるには?
課題解決型のグループディスカッションの特徴は、以下の通りです。
- ゴールが決まっている
- アイデアの現実性が大事
- 課題の分析が大事
課題解決型のグループディスカッションの具体的な進め方について早く知りたい人は以下のボタンをクリックです。
二者択一型
二者択一型のグループディスカッションとは以下のようなものをいいます。
- 無人島に持っていくならナイフかライターどっち?
- アンドロイドとiPhoneどちらを使うべき?
- 中学に制服はいる?いらない?
- 給食は無料になるべき?それとも有料?
二者択一型の質問には以下の特徴があります。
- 答えが最初から2つしかない
- 答えに辿り着く根拠が大事
- 比較検討の繰り返し
二者択一型のグループディスカッションの具体的な進め方について早く知りたい人は以下のボタンをクリックです。
自由討論型
自由討論型のグループディスカッションには以下のようなお題があります。
- 幸せとは何か
- 都内で次に流行るスイーツは何か
- ギャンブル依存症はどうすれば治るか
- 日本のIT化が遅いのはなぜか
- 新卒が入るべき会社の条件とは何か
自由討論型はとても幅が広く、さまざまなお題が出されます。
自由討論型のグループディスカッションの特徴は以下の通りです。
- 議論の内容よりも人柄が見られるケースが多い
- 発想力が重視される
- 議論をまとめる力も見られている
二者択一型のグループディスカッションの具体的な進め方について早く知りたい人は以下のボタンをクリックです。
課題解決型のグループディスカッションの進め方を紹介

ここからは課題解決型グループディスカッションの進め方を紹介します。
改めてになりますが、課題解決型のグルディスとは以下のようなものです。
- 渋谷のスタバの売り上げを2倍にするには?
- タクシーの売り上げを上げるには?
課題型のグルディスでは、以下のような流れで進んでいくことが一般的です。
前提確認→現状分析→課題特定→打ち手立案→打ち手評価
今からこのステップを一つずつ紹介していきます。
前提確認
前提確認とは「皆で共通認識を持つ」ということです。
例えば、「とある飲食店の売り上げを2倍にせよ」というお題だとします。
この「とある飲食店」と言うのが、「サイゼリヤ」だったり、「一蘭」だったり人によって違いますよね。
なので、曖昧な言葉やお題に対して共通認識を持つことが必要になります。
これが「前提確認」と言われることです。
この前提でズレがあるとその後の議論がうまく進まなくなるので、前提はしっかりとすり合わせるようにしましょう。
現状分析
現状分析とは、文字通り現状を分析し、「どこがネックになっているか」確認することです。
例えば「マクドナルドの売り上げを上げるには?」がお題だとします。
この場合、現状分析は以下のようにできます。

マクドナルドだと、昼はいつ行っても混んでますよね。
でも、平日の夜と休日の朝は割と空いています。
つまり、マクドナルドの売り上げを上げるのであれば、平日の夜と休日の昼に施策を打つことことが効果的であることがわかりました。
このようにお題の現状を細分化して分析する工程を「現状分析」を呼びます。
課題特定
課題特定は、現状分析とつながっています。
現状分析をすると、いくつかの課題が出てくるでしょう。
その課題の中で、改善した場合に最も大きなインパクトを残せる課題を特定します。
最も大きなインパクトを残せる課題を特定することで、その課題を改善すれば最も大きな変化を起こせるからです。
先ほどのマクドナルドの例で言うと、「平日の夜」と「休日の朝」の場合には、「平日の夜」の方がインパクトが大きな課題でしょう。
何故なら平日の夜の方が、休日の朝に比べて外出中の人が多いからです。
打ち手立案
ここからは今出た課題を解決するためのアイデア出しの時間になります。
ここではなるべくたくさんのアイデアを出してください。右脳をたくさん使いましょう。
今回のマクドナルドの例だと、
- 夜にハンバーグレストランとして、ハンバーグを提供する
- 夜用にカロリーが低いメニューを提供する
- ビーフシチューの提供をする
などが考えられるでしょう。
打ち手の立案の時は現実性などは考えず、とにかくいろんな案を出すようにしましょう。
打ち手評価
最後のステップである打ち手評価では、出たアイデアを評価します。
どのアイデアが一番クリティカルに影響しそうか、どのアイデアが一番実行できる可能性があるかを考えましょう。
おすすめの評価基準軸は、「現実性」と「インパクト」を総合的に評価する方法です。
そこで出たアイデアが「結論」となります。
これで課題解決型のGDは終了です。
二者択一型のグループディスカッションの進め方を紹介

ここからは二者択一型グループディスカッションの進め方を紹介します。
改めてになりますが、二者択一型のグルディスとは以下のようなものです。
- 今から言語を学ぶとしたら、「中国語」か「英語」どっち?
- 無人島に持っていくなら「ナイフ」か「ライター」どっち?
この二者択一型のグループディスカッションの流れは以下のようになります。
発散&収束→軸の決定→発散&収束
詳しく説明していきます。
発散&収束
今回は「無人島に持っていくなら、ナイフかライターどっち?」というお題に沿って話していきます。
まずは、ナイフとライターで出来ることを可能な限り挙げていきます。

ここで出た例をグルーピングしていきます。
ナイフの場合、
- 「切れる」
- 「身を守れる」
の2つの観点にまとめられます。
これが、発散&収束のプロセスです。
ここでのコツは「とにかくたくさんのアイデアを出すこと」です。
現実的にならず、「ナイフがあったら何ができるから、ライターがあったら何ができるかな」と想像を膨らましましょう。
軸の決定
先程のステップで出てきたアイデアを元に、軸を決めます。
例えば、「無人島でずっと暮らしていくためにはどちらがいい?」という軸だとします。
その場合は、「ナイフ」の方が有用でしょう。
ですが軸が「無人島で一日暮らすためにはどちらがいい?」だったら、
「ライター」の方が使い勝手が良いかもしれません。
このように軸の決定は、グループによって異なるので、正解はありません。
自分たちで前提を決めて、その前提に当てはまる項目が多い選択肢を選ぶようにしましょう。
発散&収束
軸が決まったら、「ナイフ」と「ライター」どちらがその軸に当てはまっているかを考えます。
陥りやすいのが、「ライターはダメだからナイフにする」と言ったようなパターンです。
片方に偏りすぎることはよくないです。
あくまでも公平な視点から考えましょう。
2つ目のステップで出てきた軸を元に、どちらの選択肢が良いのかを決めて、面接官に話して終了です。
自由討論型のグループディスカッションの進め方を紹介
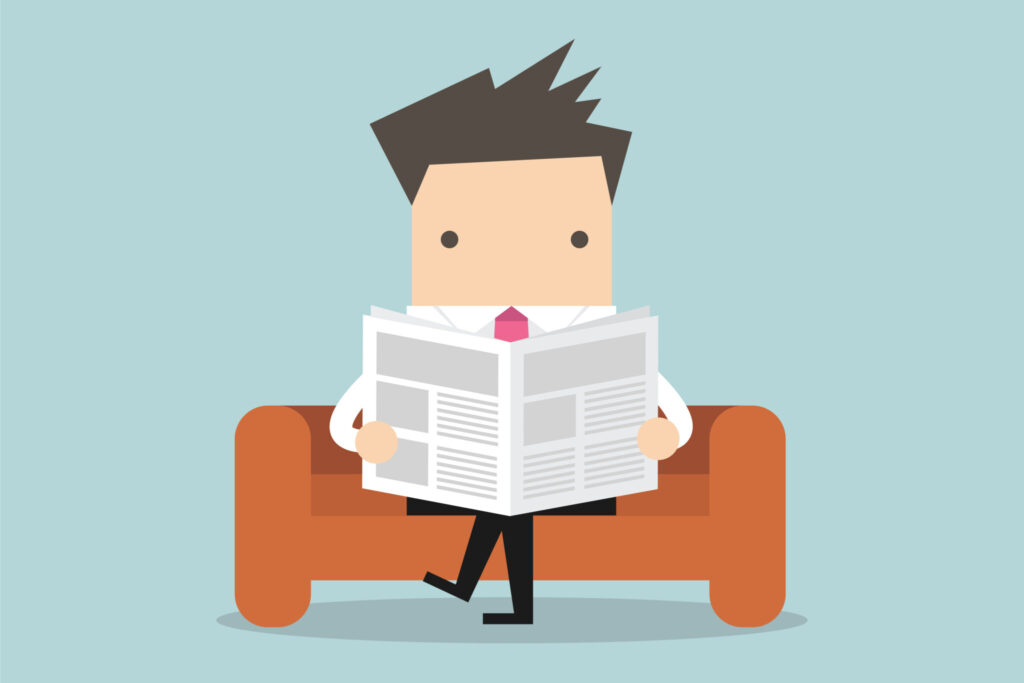
ここからは二者択一型グループディスカッションの進め方を紹介します。
改めてになりますが、二者択一型のグルディスとは以下のようなものです。
- 幸せな職場とは?
- 新卒が入社するべき会社の条件とは?
この自由討論型の1番の特徴は、「お題がフワッとしてる」点です。
つまり、共通認識を持つことが何よりも大切となるということです。
自由討論型のグルディスの流れは以下のような感じです。
発散→収束
詳しく解説していきます。
発散
今回のお題は「幸せな人とは?」で話していきます。
いきなり「幸せな人ってこんな人だよね」と決め切るのは難しいです。
なので、まずは「周りにいる幸せの人の特徴を教えて」みたいな感じで、幸せな人の条件を探っていきましょう。
ここでのコツはなるべく多くのアイデアを出すことです。
この後のステップでグルーピングをするため、ここでは粒度などは気にせずとにかく自分が思った事を発言しましょう。
収束
出てきたアイデアをグルーピングしていきます。
グルーピングとは、「この話とこの話、本質的には同じことだよね」みたいに、似ている事象をまとめていくことです。
そうすると大体2つか3つくらいにまとまるでしょう。
今回のお題の場合だと、
- 自分の好きなことを仕事にできている人
- お金に余裕がある人
などに落ち着くかもしれません。
そこからはグループで一番納得できる選択肢を選びましょう!
もし時間があれば、具体的な経験や理由を付け加えることをおすすめします。
例えば、「私って〇〇な経験をして、その時幸せだったんだよね」みたいに、実体験を入れるのもありです。
グループディスカッションを行う意図とは?

まずは企業がグループディスカッションを行う理由から知ることで、グループディスカッションへの理解が深まります。
グループディスカッションを企業が行う理由は以下の3つです。
- 短時間で多くの学生を選考できる
- 地頭力を見れる
- 協調性を見れる
順番に説明していきます。
短時間で多くの学生を選考できる
グループディスカッションは最低3人、多くて6人程度の人がグループになって選考を行います。
つまり、30分で6人程度の就活生を選考することが可能です。
グループ面接だとしても選考できるのは、1時間で3人程度ですよね。
通常の面接となると、30分で1人の面接をします。
なので、グループディスカッションは企業からすると圧倒的に時間効率が良い選考手段なのです。
そのため、グループディスカッションは足切りの選考として出てくることが多いです。
地頭力を見れる
グループディスカッションでは初見のお題に対して時間内に最適な回答を作成することが求められます。
すなわち地頭力が試されるということです。
これは面接では計測することができない能力です。
なぜなら、面接は準備しようと思えば、いくらでも準備ができるからです。
面接の対策方法を知りたい人は以下の記事がおすすめ
協調性を見れる
面接は面接官と就活生の一対一での対話形式なため、他の仲間とどのようにコミュニケーションを取るのか確認することができません。
グループディスカッションをすることで、その学生が他の学生とどのように協力しながら問題解決するのか確認することができます。
会社で働くとなると、それぞれと協調しながら働くことが求められます。
協調力は会社に入ってから非常に重要なので、グループディスカッションを通じて観られるのです。
グループディスカッションでの役割
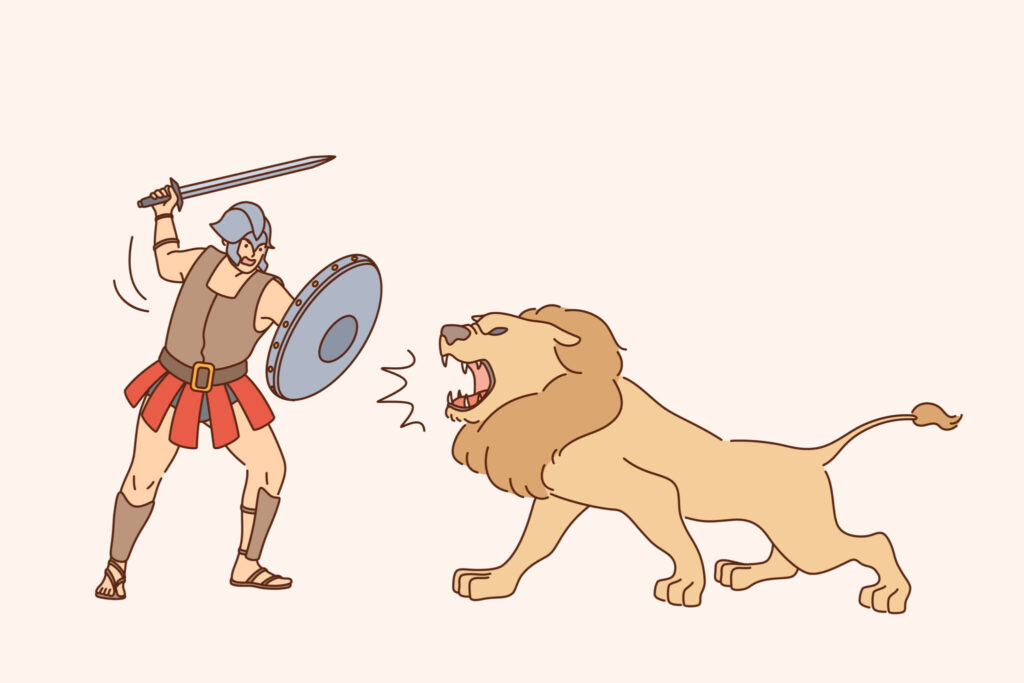
グループディスカッションにはどのような役割があるのでしょうか?
一般的には以下の4つの役割があると言われています。
- リーダー(ファシリテーター)
- 書記
- タイムキーパー
- それ以外の人
それぞれの役割について深く知りたい人は以下の記事を参考にすると良いでしょう。
悲報:役割は必要ない
ただ、私の意見としては「これらの役割はあってないようなもの」であると思います。
リーダー以外の人が議論を仕切ったらダメなわけでないですし、書記以外の人がメモを残したらダメなわけではありません。
後ほど詳しく説明しますが、グループディスカッションで大事なことは「チームとして最高のアウトプットを出すこと」です。
なので、チームとして足りていない箇所に自分が入り、そこを補填するのがグループディスカッションで取るべき役割なんですね。
ちなみに私はグループディスカッションをするときはいつも「チームとして最高のアウトプットを出すならどうするべきか」というのを考えていました。
その結果、グループディスカッションでは勝率8割以上を叩き出すことができました。
グループディスカッションで評価されるポイントを解説

ここからはグループディスカッションで評価されるポイントを紹介します。
以下のポイントを面接官は見ている可能性が高いです。
- コミュニケーション能力
- 協調性
- 論理的思考力
- 発想力
- まとめる力
順番に解説します。
コミュニケーション能力
一対一のコミュニケーション能力を見たいのであれば、面接でも見れます。
なので、グループディスカッションを通じて見ているコミュニケーション能力は、チームメンバーとのコミュニケーション能力です。
仕事は一人で進めることはほぼなく、誰かしらと連携をしながら進めていきます。
そのときにどのようにステークホルダー(関係者)に接するのかをグループディスカッションを通じて見ているのです。
多少能力が低くても、コミュニケーションをとって、周りを巻き込んでいける人は強いです。
協調性
グループディスカッションをする際に評価するポイントの2つ目が協調性です。
もし仮に他の人がトンチンカンな発言をしても、否定的にならず、その発言に対して優しく接することができているかなどを見ています。
協調性を見せるために大事なのは、否定から入るのではなく、「確かにそうですね、ですが」のような肯定から入ることです。
また、「周りと自分の意見が一致しているときは賛同をしっかりするのか」なども見られています。
論理的思考能力
グループディスカッションは「お題についてみんなで話し合い、結論を出す」選考です。
基本的に結論の鋭さやアイデアの新規性などはそこまで問われません。
大事なのは、その結論に至る過程で、どのような論理が組まれたかです。
例えば…
お題が「赤い果物は?」だとします。
出た結論が、「りんご」だとします。
面接官が「なぜりんごとしたのですか?」と聞いた時に、
「それが唯一の赤い果物だからです」と答えてはダメですね。
なぜなら「イチゴ」も赤い果物だからです。
これでは、論理的に構造的に考えられていないため、高い評価をもらうことは厳しいです。
この「漏れなくダブりなく」の考え方は、MECEと呼ばれていて、コンサル業界などでは多用されているフレームワークです。
ぜひ覚えて、グループディスカッションで使いましょう。
発想力
グループディスカッションでは、発想力が求められる瞬間が多いです。
例えば「幸せな人とはどんな人?」というお題だとすれば、幸せな人はどんな人か考える必要があります。
そのときにたくさんアイデアを出せる人は議論を前に進めることができ、良い評価を得ることができます。
グループディスカッションでは限られた時間内で結論を出す必要があるため、発想力が鍵になることもあります。
まとめる力
議論をまとめる力も大きく評価されるポイントの一つです。
グループディスカッションは初対面の人たちが時間内に結論を導くためにさまざまな議論をします。
その結果、議論の内容が本質とは関係ないところに行ってしまうこともあります。
そうなってしまっては議論をしている意味がありません。
そこで議論を修正して、まとめる力がある人がいると議論がまっすぐ進みます。
なので、議論をまとめる力がある人も評価されます。
グループディスカッションで気をつけること
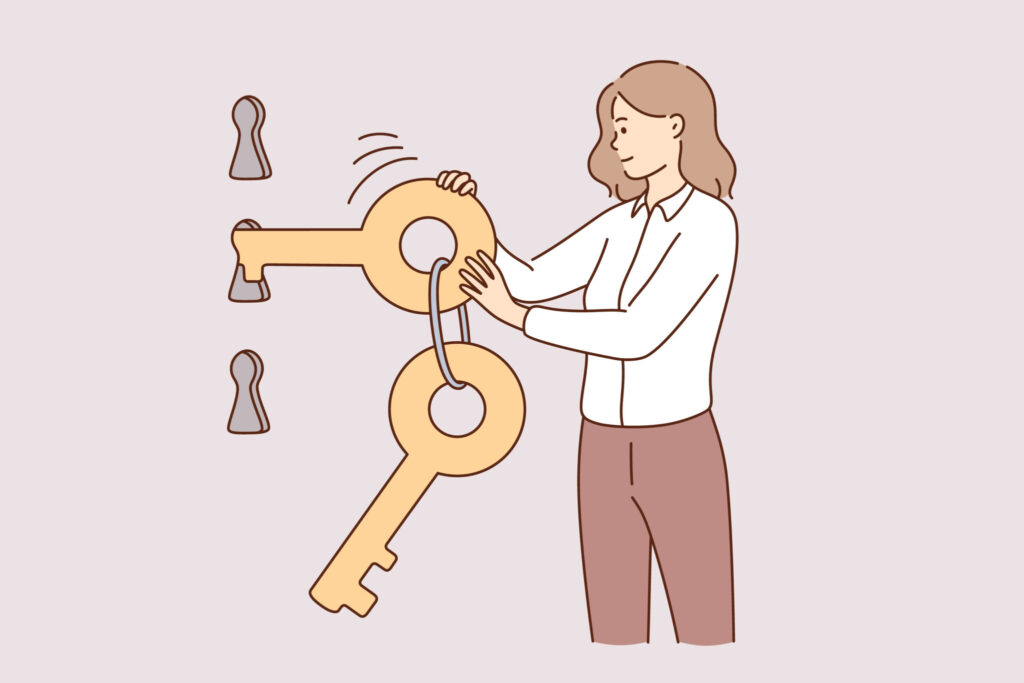
ここからはグループディスカッションで気をつけるべき注意点について解説します。
以下の4つの点には気をつけましょう。
- 周りの発言にしっかり耳を傾ける
- わからないことがあったらすぐ聞く
- 大きな声で発言する
- 考えるときの癖に注意する
順番に解説します。
周りの発言にしっかり耳を傾ける
グループディスカッションをしていると、どうしても考え込んでしまう時間があると思います。
そういったときに自分の世界に入り込んで考える人がいます。
これは面接官からみると、良い印象ではありません。
他の人が話しているときにはその人が言っていることに耳を傾けましょう。
わからないことがあったらすぐ聞く
グループディスカッションにおいて、一番の時間の無駄は議論したところへ再度戻ることです。
短い時間の中で結論まで辿り着く必要があるため、一度議論したところを再度議論するのは大幅な時間ロスです。
なので、もしわからないことや議論したいことがあったら積極的に発言しましょう。
何度も言いますが、後から戻って議論するのは本当に時間がもったいないです。
大きな声で発言する
グループディスカッションでは多くの人が同時に発言したりするため、小さな声で喋っていては、誰も拾ってくれません。
なので、大きな声で発言するようにしましょう。
最近はオンライン開催が多いため、オンラインの場合はマイクを自分の口に近づけるなどの対策を取りましょう。
考えるときの癖に注意する
皆さんは考えるときに何か癖があったりしませんか?
例えばペン回しをする人だったり、髪の毛を触る人だったり。
こういった癖がある人は、癖に注意しましょう。
まとめ
ここまで記事を読んでいただき、ありがとうございます。
今回はグルディスの全てを紹介しました。
グルディスは、流れがわかるようになれば簡単な選考です。
今回記事で紹介した内容をぜひ覚えていきましょう。
この記事を読んでいる人には以下の記事がおすすめです。