巷で「持ち駒」って言葉を聞いたけど、これってどういう意味なの?
また、平均的な持ち駒の数ってどんくらいなの?

巷で「持ち駒」って言葉を聞いたけど、これってどういう意味なの?
また、平均的な持ち駒の数ってどんくらいなの?
みなさんはこういった疑問をお持ちではないでしょうか?
この記事はそんなみなさんにぴったりの記事となっています。
この記事を読むとわかること
就活のゴールである内定を取れる確率は人によって違います。
なので人によって受けるべき企業数も変わってきます。
私は就活生の時に「どれくらいの企業数を受ければいいんだろう」と疑問に思っていました。
おそらくこの記事を読んでいる皆さんも疑問に思っているでしょう。
なのでこの記事では「就活生の平均持ち駒数」から「私がおすすめする持ち駒数」まで解説していきます。
それでは早速いきましょう!
具体的な持ち駒の数などの話に入っていく前に、持ち駒について少しだけ共有です。
持ち駒とは選考を受けている、もしくは受ける予定の企業のことを言います。
なので、選考に落ちてしまった企業は持ち駒ではありません。
Aさんが選考を受けている企業が5社で、選考を受ける予定の企業が10社の場合、持ち駒の合計は15になります。
就活をしていると疑問に思うことが「どれくらい持ち駒を持っておくのがベストなの?」ということだと思います。
まずは就活生の平均持ち駒数と平均内定社数を紹介していきます。
マイナビが行った調査によると、就活生の平均エントリー数は20.7社であることがわかりました。
この数値は年々低くなっていると言われています。
理由は就活の早期化や短期化に伴って、少ない企業に深く時間を割いていく就活生が増えているからです。
リクルートの就活みらい研究所が調査した内容によると、就活生の平均内定社数は、2.17社であります。
この数字は2018年の就活からずっと下降トレンドにあります。
ここからは就活生が内定の数ではなく、本当に行きたい企業から内定をもらうことにフォーカスしていることが読み取れます。
私は就活生時代にサマーインターンやウィンターインターンなどの選考を含めると50社近くにプレエントリーをしました。
その中で面接を受けたのがおそらく20社くらいで、最終面接を受けたのが3社となっています。
本選考だけで数えると、15社程度受けました。
ぶっちゃけた感想を言うと、ウェブテストやESに通っても面接を受けなかった企業などもあり、こんなに受ける必要は絶対になかったと思います。
ということで、20社以上の持ち駒は持っておくと良いでしょう。
20社よりも少ないと持ち駒がなくなってしまうなどの問題がありそうです。
ここからは持ち駒が多いこと・少ないことのメリットを解説します。
まずは持ち駒が多いことによるメリットです。
持ち駒が多いことによる一番のメリットは心の余裕を生むことができることです。
持ち駒が少なくなると、「この中からなんとしても内定を取らなくてはいけない」という気持ちに駆られます。
するとメンタルが健康な状況ではなくなるため、就活の成績にも影響が出ます。
しかしながら持ち駒が多いと「まだ大丈夫だな」という気持ちになれるため、心に余裕が生まれるんですね。
メンタルの話なんて馬鹿らしいと思った人もいるかもしれませんが、非常に重要な話です。
次は持ち駒が少ないことによるメリットです。
やはり持ち駒を減らして就活をすることの最大のメリットは、一つ一つの企業に多くの時間を割けることでしょう。
就活って意外と時間との戦いのため、企業研究や自己分析に多くの時間を割けることは非常に有益です。
また、行く気がそうそうない企業の選考を受けずに済むこともメリットの一つです。
私が思う就活生にとってベストな方法は、「持ち駒をなるべく多く持っておく」ことです。
いや、さっき無駄に選考を受けて時間を損したとか言ってたじゃん
確かに無駄に時間をしてしまったのですが、それはあくまでも結果論です。
結果的にいきたい企業から内定をもらうことができたので、行きたくもない企業の選考を受ける意味はなかったのですが、もしかしたら希望する企業から内定をもらえない可能性だってあったかもしれません。
持ち駒とメンタルは密接です
私が持ち駒を多く持っておいた方がいいとお勧めする理由は「メンタル面」です。
やっぱり持ち駒が少なくなってくると、メンタル的にくるんですよね。
特に就活が終わりに近づいてくると、選考を受けるにも企業が絞られちゃうし、今さら企業研究しても間に合わないしといった感じになりますよね。
なので、最初は持ち駒を多くしておいて、ある程度気に入っている企業から内定をもらえたら、あとは本当に受けたい企業だけを受けるようにしましょう。
この記事を読んでいる人で、持ち駒を20社以上持っておくなんて難しいと思っている人もいるでしょう。
そんな人は以下の点をチェックするとなぜ持ち駒が少ないのかわかります。
大企業しか受けていない人は持ち駒がなくなりがちです。
そもそも大企業は就活難易度が高く、優秀な人でも内定をもらうのが難しいです。
また、大企業はそもそも母数も少ないです。
なので、大企業しか受けていない大手病の人は持ち駒が少なくなりがちです。
業界を絞りすぎると、受けることができる企業数が非常に少なくなります。
例えばメーカーを志望している人で、お菓子メーカーを志望している人がいたとします。
お菓子メーカーなんてそんなに多くの数があるわけではないですよね。
その中で新卒採用をしているお菓子メーカーなんて数えられるくらいでしょう。
なので、業界の絞り過ぎもよくないです。
持ち駒がなくなってしまった時の対処法を紹介します。
順番に解説します。
就活エージェントとは、一言で言うと就活のプロです。
みなさんが内定を取れるまでサポートしてくれるサービスとなっています。
もちろん学生は無料で使えます。
就活エージェントの特色はもちろん内定までサポートしてくれるというのがあるのですが、それ以外にも「就活サイトで発見できない求人に出会える」というのがあります。
なので、就活エージェントを使うことで今まで見たことがない求人に出会えたりします。
ただ、就活エージェントによっては学生のことを悪く扱うところもあります。
なのであまり就活エージェントに詳しくない人は以下の就活エージェントをまずはチェックしてみると良いでしょう。
・JobSpring→圧倒的に丁寧な就活エージェント。本当におすすめする3社〜5社を紹介するため、学生に良心的。また、自己分析テストをもとに就活相談を進めてくれる。女性の利用率が7割を超えているため、女性も安心。中の人が実際にインタビューをして、おすすめできるか確認済み。
・irodasサロン→年間利用者数が13,000人の超大手就活エージェント。コミュニティ型となっており、就活生同士での密な連絡も可能です。そのため、満足度が脅威の95%となっている。就レポでは口コミ数1位。
・キャリアチケット→就活生にも大人気の人材系企業レバレジーズ株式会社が運営する就活エージェント。1万人以上の就活生にアドバイスをしてきたコンサルタントが圧倒的な質のサービスを完全無料で提供。最短2週間で「内定」までいけるのはキャリアチケットのみ。
大学のキャリアセンターにも通常の就活サイトとは違った求人が掲載されています。
また、大学のキャリアセンターの求人は優遇などがある場合も多く、内定までの距離が近いものが結構あります。
なので、大学のキャリアセンターに行って、新しい企業を探すというのは結構ありです。
就活サイトには常に新しい求人がどんどんと公開されていきます。
なので、就活サイトをこまめにチェックして新しい求人が出てるかどうかチェックするのはおすすめです。
特に就活サイトによって求人の特徴に差があるため、就活サイトはできるだけ多くの就活サイトを確認することをおすすめします。
私は以下の2つの就活サイトをメインにして就活をしていました。
One Career→難関大学出身の就活生使用率No.1の就活サイト。ここでしか載っていない選考情報あり。先輩たちが書いたESや面接で聞かれた質問が書いてある「選考体験レポート」がかなりやばいです。(さらに詳しく知りたい人はこちら)
unistyle→10,000枚以上のESが読み放題の就活サイト。ESに苦戦している人は絶対に登録するべき。LINEのオープンチャットがあり、就活に関する情報を最速でキャッチできる。LINEのオープンチャットのためにも登録しても良いくらい。(さらに詳しく知りたい人はこちら)
ここからは私が持ち駒を管理していた方法を紹介します。
エントリー数が多くなるにつれて、自分の受けている企業の管理が難しくなっていきますよね。
そんな人に使って欲しいのが、私が作った持ち駒管理スプレッドシートです。
私は就活生時代、これに全ての選考を受けた企業を書き込んでいました。
非常に管理しやすかったので、ぜひ使ってみてください。
実は選考を受けた後の振り返りシートもついています。
※もしよかったら、このサイトを友達や知り合いに教えてくれると嬉しいです。
無料でできるので、よろしくお願いします。
ここまで読んでくださって、ありがとうございます。
今回は持ち駒数の平均について解説しました。
このサイトでは他にも就活生にとって有益な情報をたくさん発信しているので、気になる人はぜひ。
人気の記事
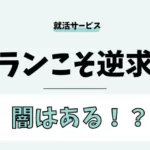 1
1
Fラン生こと逆求人使って欲しいんですが、話題の逆求人サイトってスカウトが来るって聞いたんだけど、なんか怪しいんだよな。 みたいな事を思ってる人も多いのでこういった疑問を解決します。 この記事を読むとわ ...
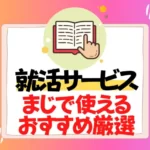 2
2
私は23卒就活生でしたが、早期選考で某有名ITベンチャーから内定をもらい、就職活動を終えました。 就職活動自体は半年ほど行なったのですが、その中で自分が愛用していたサイトやサービスを今回はまとめていき ...