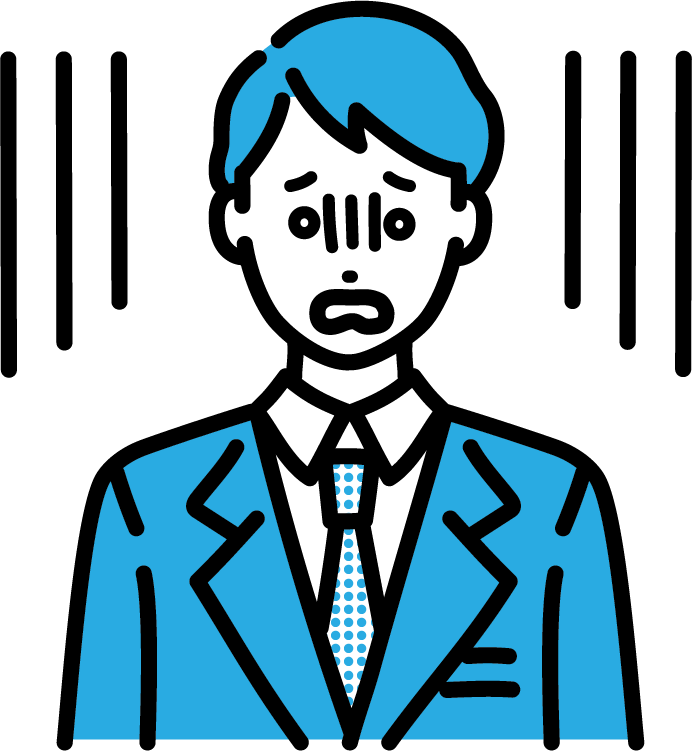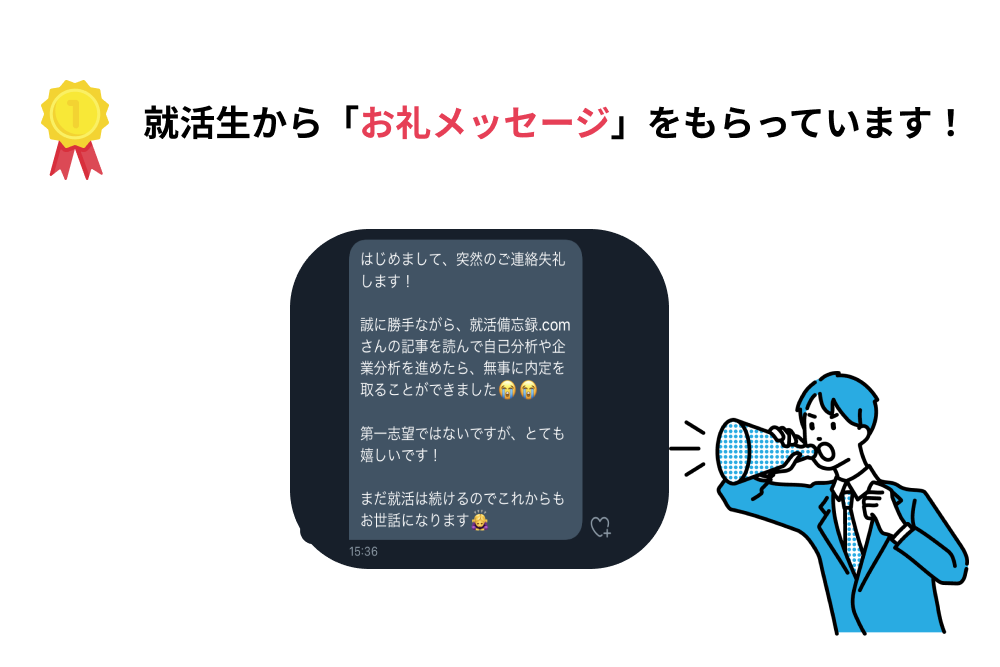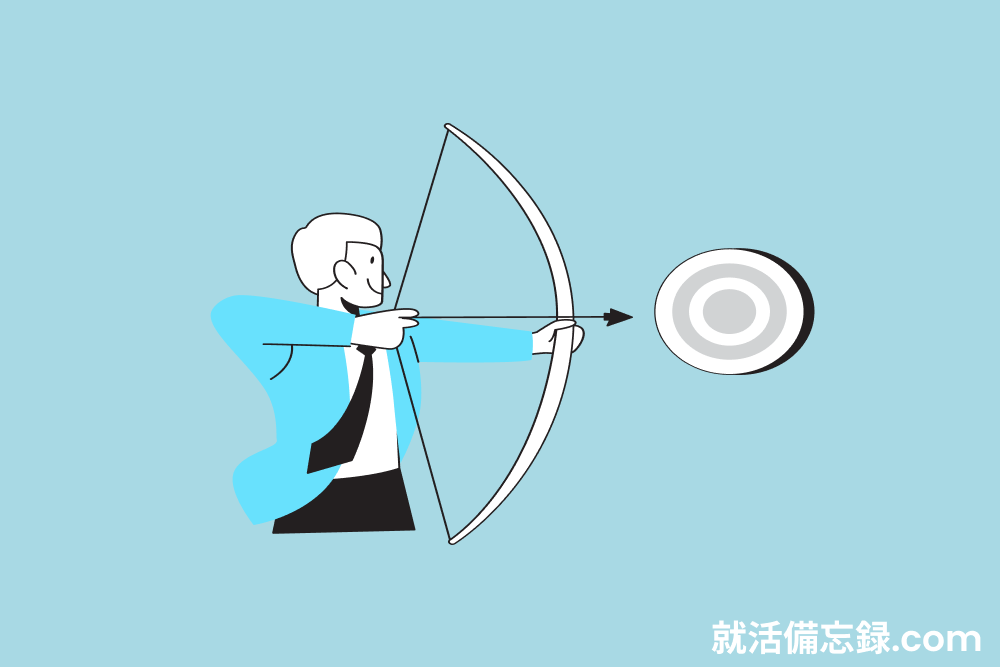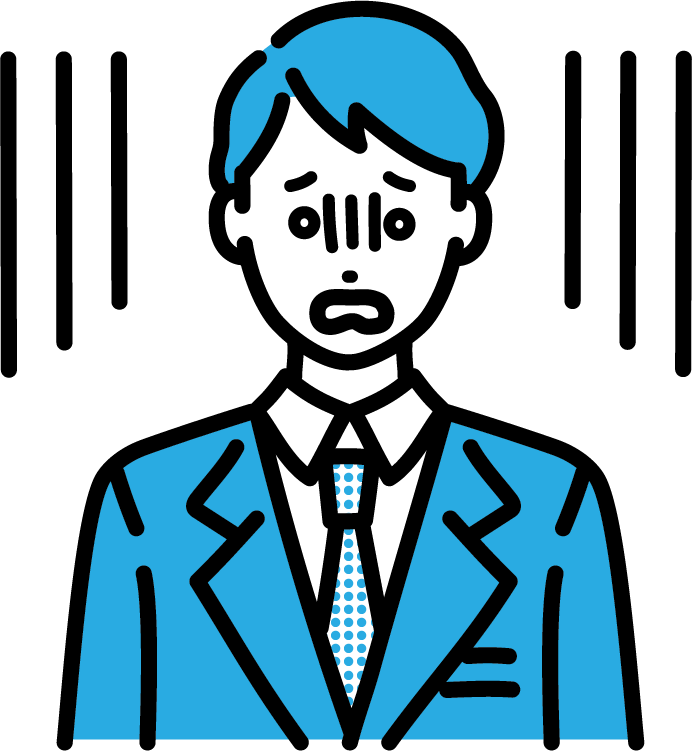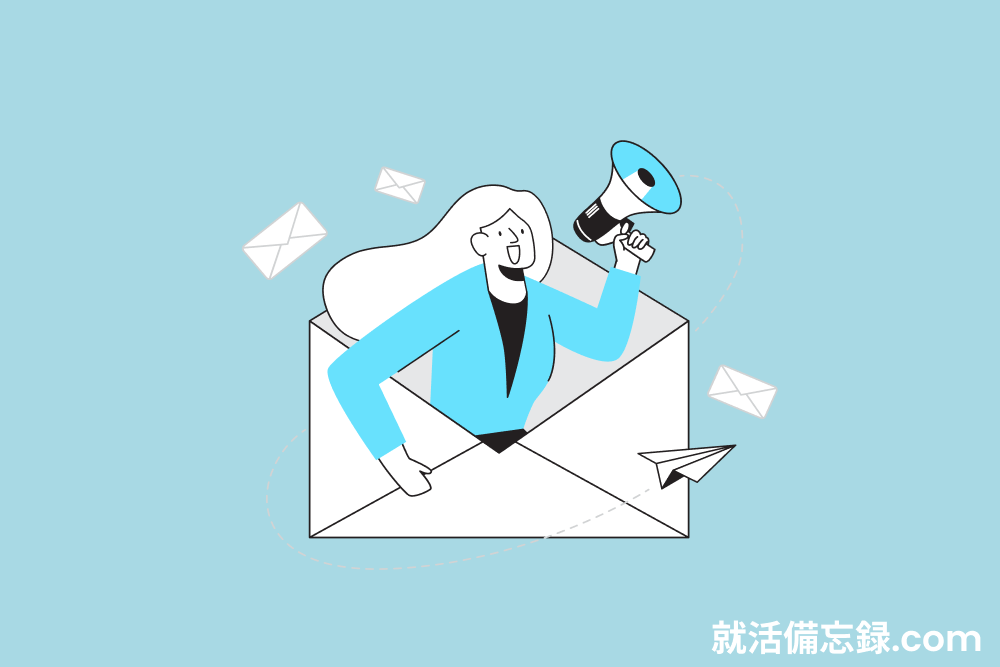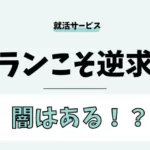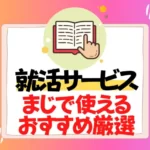面接
【22卒が語る】就活の面接対策はいつから始める?スケジュールを理解し、対策しよう。
就活生
就活の面接対策はいつからするべき?
面接の対策方法はどんなものがある?
就活のスケジュールが知りたい
みなさんはこういった疑問をお持ちではないでしょうか?
この記事はそんなみなさんにぴったりの記事となっています。
✔️この記事を読むとわかること
- 就活の面接対策を始める時期
- 就活のスケジュール
- おすすめの面接対策
- 面接を通過するコツ
それでは早速解説していきます!

面接対策はいつから始めるべき?

就活における面接対策はいつから始めるべきなのでしょうか?
まず前提として、面接の対策はできるだけ早く始めるべきです。
なぜなら、面接は「経験」が大事だからです。
みなさんがもし何回も面接を受けたことがあるなら、一番最初に受けた面接と最近受けた面接を比較してみてください。

インターン前と本選考前に始めるのもおすすめ
選考がない時に面接対策をするのは馬鹿らしいと感じる人もいるでしょう。
そういった人におすすめなのが、サマーインターン・ウィンターインターン・本選考の前に面接対策を始める方法です。
時期で言うと、3年生の6月、11月、2月ごろに対策をすることになります。

就活のスケジュールを解説します


就活生
まずそもそも就活のスケジュールがわからないよ…
という人もいるではないでしょうか?
特に最近は就活の早期化が顕著になっており、ネットに公開されている情報の通りに就活が進まないことも多々あります。

の3つに分けて説明します。
日系大手の就活スケジュール
日系大手を目指す就活生はとても多いと思います。
日系大手の就活スケジュールは3月にある本選考を中心として組み立てるべきです。
なので、以下の画像のような就活スケジュールで就活をすることをおすすめしています。

詳しく知りたい人は以下の記事を参考にすると良いかもしれません。
外資系の就活スケジュール
外資系企業、私も就活でたくさん受けていました。
高い給料や自由な社風が魅力的ですよね。
外資系企業の就活の特徴は「とにかく早い」ことです。
3年生の12月までに内定が出揃う企業もたくさんあります。
具体的には以下の画像のように動くことを外資系就活をしている人にはおすすめしています。

もっと深く知りたい人は以下の記事を参照にすることをおすすめします。
ベンチャー企業の就活スケジュール
ベンチャー企業を受けたい、ベンチャー企業に就職したいという人は近年増えてきていますよね。
この記事を執筆している私もベンチャー企業に就職します。
ベンチャー企業の就活スケジュールの特徴は、早くから選考を行っていることです。
具体的には以下の画像のような就活スケジュールになります。

面接の対策方法3つを紹介します!

面接は対策をしっかりすることで「圧倒的に」通過率を上げることができます。
これは模擬面接を30回以上行っていた私が明言します。
なのでここからは私がおすすめする面接対策方法を紹介します。
具体的には以下の3つの方法で面接の対策をしましょう。
- 想定質問リストを作る
- 模擬面接をする
- 志望度の低い同業他社で面接練習
一つずつ説明します。
想定質問リストを作る
変な質問ですが、面接で聞かれる質問があらかじめ分かれば、面接を通過できると思いませんか?
それを可能にするのが、想定質問リストです。
過去に聞かれた質問を元に、面接でどんな質問が聞かれそうか予測し、その質問への回答を作成する方法です。
私は大事な企業の面接の前にはこの想定質問を30個程度作ってから面接に臨んでいました。

就活生
でもどうやって、過去に聞かれた質問を見つけるの?
結論を言うと、「ワンキャリア」や「unistyle」といった就活サイトに載っている「先輩たちの選考体験記」を見ればわかります。
ワンキャリアとunistyleの説明は以下に載せておきます。
One Career→難関大学出身の就活生使用率No.1の就活サイト。ここでしか載っていない選考情報あり。先輩たちが書いたESや面接で聞かれた質問が書いてある「選考体験レポート」がかなりやばいです。(さらに詳しく知りたい人はこちら)
unistyle→10,000枚以上のESが読み放題の就活サイト。ESに苦戦している人は絶対に登録するべき。LINEのオープンチャットがあり、就活に関する情報を最速でキャッチできる。LINEのオープンチャットのためにも登録しても良いくらい。(さらに詳しく知りたい人はこちら)
模擬面接をする
先ほど「面接は経験がものを言うゲーム」と言いました。
その経験値を積むためにおすすめなのが模擬面接です。
模擬面接とは、本番の面接を想定して面接練習をすることを言います。

 就活生
就活生
でも模擬面接ってどうやるの?
って思った人いると思います。
模擬面接のやり方がわからない人は以下の記事を参考にすると良いかもしれません。
私が30回以上行って編み出した模擬面接の方法が書いてあります。
志望度の低い同業他社で練習
面接の練習をするなら、本番の面接と同じ環境で練習をするのが一番と考える人もいるでしょう。
そんな人におすすめなのが、志望度の低い同業他社で面接練習をすることです。
例えば、メガバンクが第一志望の人がいたとします。
その人はメガバンクでの面接を完璧にするために、どこか田舎の地方銀行の面接を受けるのが良いでしょう。
なぜなら同じ金融ということで志望動機もある程度被りますし、銀行で求めらている人は大抵一緒です。
なので聞かれる質問も同じような質問が聞かれることが多いでしょう。
この方法のメリットは、
- 本番と同じ緊張感が味わえる
- 同業他社のため、質問内容が似ているから回答を作る準備になる
- 受かったら自信がつく
といった感じです。
この対策方法を取る場合に絶対やって欲しいことがあって、それは「面接で聞かれた質問を全て記録に残す」ことです。
これをすることで、皆さんの本当の第一希望の企業の面接の通過率を上げることができるからです。
面接を通過するコツ4つを紹介します。

この記事の最後に面接を通過するためのコツを紹介します。
具体的には以下の4つの点を意識すると面接の通過率を上げることができます。
- 相手に伝わっているか確認しながら話す
- 志望度の高さをアピールする
- 自分が活躍できるイメージを相手に持たせる
- 一貫性を保つ
順番に解説します。
相手に伝わっているか確認しながら話す
みなさんは面接官が理解しているのを確認しながら話していますか?
残念ながら就活生に多いのが自分本位でガクチカや自己PRをしゃべってしまい、面接官に伝わっていないパターンです。
面接は面接官と就活生の会話のキャッチボールの場所で、自分が話したいことを話す場所ではありません。
なので、面接官が自分の話したい内容を理解しているのか確認しながら話すことは、面接の通過率を上げるために重要になります。
おすすめの方法は少ししゃべった後に「ここまでで疑問点はございますか?」と面接官に聞くことです。
面接官からしても「この子は相手に気を配れる優秀な学生だ」と思ってくれるでしょう。
志望度の高さをアピールする
みなさんは志望度の高さをしっかりアピールできていますか?
企業の採用担当者は学生が思っている以上に志望度を重視しています。
私は長期インターンの経験もあるし、英語も喋れるから就活は余裕だろうとあぐらをかいており、全く志望度の高さをアピールしませんでした。
案の定、全く面接に受からない日々が続きました。
企業側からすると「学生でインターンやってました」とか「留学行ってたので英語が喋れます」とかってどんぐりの背比べなんですよね。
バリバリ働いている社会人から見れば、どの学生の能力も同じようなものです。
そこで差を作るのが、志望度の高さです。
企業からするとやっぱり志望度の高い学生を取りたいと思いますし、志望度の高い学生の方がすぐ辞めないと確信できますからね。
なので、志望度の高さをアピールするようにしましょう。
ちなみに志望度の高さをアピールするときには以下の点を意識するといいでしょう。
- 声の大きさを一段階あげる
- 体を前のめりにする
- ロジックよりも熱意でゴリ押す
自分が活躍できるイメージを相手に持たせる
当たり前ですが、企業という組織が新卒を取るのは、会社にとって利益があるからです。
もし新卒を取ることによるメリットがない場合は、中途採用でいいですからね。
ではどのようにして「会社にとって利益がある人間である」ことを証明するのが良いでしょうか?
それは自分が活躍できるイメージを相手に持たせることです。
例えば、営業職を志望している人の場合は「私は初対面の人と打ち解けることが得意です。最近だと誰も知らないパーティーに参加して10人以上の友達を作りました」といった感じです。
この活躍できるイメージを持たせることにおいて重要なのが「OBOG訪問」です。
OBOG訪問で「現場ではどのように働いて、どのような強みを持っている人が活躍しているのか」聞いておくことで、それ通りのことを面接で話せます。
なのでまとめると、
現場で活躍できるイメージを相手に持たせるのが大事。
そのためには「OBOG訪問」がオススメ。
となります。
一貫性を保つ
みなさんは1次面接と2次面接で別々のことを言ったことはないですか?
私は全く違うことを言って、一貫性がないと言われ、落ちてしまいました。
就活の面接において一貫性というのは非常に大事です。
これはなぜかというと、新卒採用市場において企業はみなさんの性格や人となりを見て、みなさんを採用するのか決めているからです。
それなのに面接ごとに違うことを言っていたら、「この人は本当はどんな人なんだろう」と思ってしまいますよね。
なので面接では一貫性を保つことを意識しましょう。
まとめ
ここまで記事を読んでくださって、ありがとうございます。
面接対策はいつからでも始めるべきです。
なので、もし今日から始められる場合は今からでも面接対策を始めましょう。
-

-
小田楓
マーチ生だった楓です。月間1万人以上が訪れる「就活生だからこそ言えること」を伝えるサイト、就活備忘録.comを運営しています。22卒/長期インターン2社→ITベンチャーにて人事
人気の記事
-
 1
1
-
Fラン生こと逆求人使って欲しいんですが、話題の逆求人サイトってスカウトが来るって聞いたんだけど、なんか怪しいんだよな。 みたいな事を思ってる人も多いのでこういった疑問を解決します。 この記事を読むとわ ...
-
 2
2
-
私は23卒就活生でしたが、早期選考で某有名ITベンチャーから内定をもらい、就職活動を終えました。 就職活動自体は半年ほど行なったのですが、その中で自分が愛用していたサイトやサービスを今回はまとめていき ...
-面接
-対策, 面接